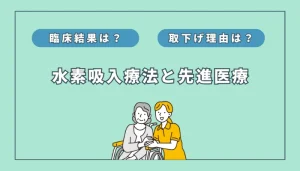水素吸入が「効果なしのエセ科学」ではない根拠
冒頭でも述べた通り、水素吸入は「効果がないエセ科学」ではありません。
その根拠として、以下の4つが挙げられます。
※タップすると該当見出しへ移動します
それぞれ詳しく解説していきます。
根拠①:先進医療として厚労省が認定した実績がある
水素吸入は、かつて厚生労働省によって先進医療Bとして認定された実績があります。効果と安全性が一定程度認められ、2016年から「心停止後症候群」に対する治療法として、実際の医療現場で使用されていました。
先進医療とは、将来的に保険診療への導入が検討される、比較的先進的な医療技術を指します。先進医療への認定は、水素吸入が全く科学的根拠のないものではなく、エビデンスに基づき、その可能性が評価されていた ことを示します。
根拠②:人を対象とした臨床研究で効果が示されたエビデンス多数
水素吸入の効果については、人を対象とした臨床研究も多く行われ、有望な結果も出ています 。
人を対象とした研究は、動物実験や基礎研究よりも信頼性があり、多数の研究結果が査読(他の研究者によるチェック)のある科学雑誌に掲載されています。さらに、こうした研究の中には、プラセボ対照試験※1 や二重盲検試験※2 といった科学的に信頼性の高い手法が用いられているものもあります。
水素吸入はそういった科学的な手法を用いて研究が進んでおり、決して「エセ科学」とは言えません。
※1 偽薬を用いて比較する試験
根拠③:医療機関で実際に治療として導入されている事実
一部の医療機関では、水素吸入がすでに自由診療として導入されています。特に、がん治療の補助療法として提供されていることが多く見受けられます。
医療機関がこの治療法を導入している背景には、医師による臨床経験や既存の研究論文に対する評価がある と考えられます。もちろん、自由診療であることや、導入している医療機関が限られているという点は考慮すべきです。
しかし、医療の現場で実際に用いられているという事実は、水素吸入療法が「全く効果なし」とは言い切れない根拠の一つ となります。
根拠④:継続的に国内外で研究が進められている
水素吸入療法は、現在も国内外で活発に研究が進められています。様々な疾患への効果や作用メカニズムの解明が目指されています。
近年は、ハーバード大学の研究者らが論文を発表するなど、欧米での注目度も高まっています。3)日本でも慶應義塾大学など権威のある大学において研究が進んでいます。4)
こうした研究が継続しているという事実こそが、水素吸入が科学的な探求の対象である証拠 と言えるでしょう。
当サイトでは水素に関連する様々な研究報告を解説しているので、興味のある方はぜひご覧ください。水素に関連する研究論文一覧【掲載数250件以上】
それでも水素吸入が「効果のないエセ科学」と言われる理由5つ
水素吸入に一定の科学的根拠や医療現場での利用がある一方で、「効果がないエセ科学」と言われる背景には、いくつかの理由が考えられます。
そもそも「効果がある」と「エセ科学」とは?
医学における「効果」とは、特定の介入(治療法など)が、期待される有益な結果を生み出す能力 を指します。これは、理想的な条件下だけでなく、実際の臨床現場においても発揮することが求められます。
一方、「エセ科学」とは、科学的なように見えるが実際には科学的方法に基づいていない主張や実践のこと を指します。主な特徴として、以下が挙げられます。
再現性のある実験結果がない
科学的根拠よりも個人の体験談や証言に基づく
科学的な検証や反証を拒否する傾向がある
血液型と性格の関連性を主張する「血液型性格診断」は、エセ科学の典型的な例の1つです。
では、水素吸入療法がなぜそういった「効果のないエセ科学」と見なされるかの理由について見ていきましょう。
主な理由として、以下の5つが考えられます。
※タップすると該当見出しへ移動します
それぞれ詳しく解説していきます。
水素吸入が効果なしのエセ科学と言われる理由①: 過去に起こった「水素水ブーム」は、水素に関するイメージを大きく損ねました。
当時、水素水は様々な健康効果を謳って販売されましたが、多くの製品で水素濃度が不十分であったり、科学的根拠に乏しい誇大広告が問題視 されていました。実際、消費者庁は、エビデンスが十分ではない効果・効能を謳って販売していたとして、複数の事業者に対し措置命令を下しました。
この水素水ブームの負の遺産が、水素吸入に対しても「どうせ効果がないだろう」「エセ科学だ」という先入観を生み出す要因 となっています。水素水と水素吸入は、水素の摂取方法や濃度が大きく異なるにもかかわらず、混同されて認識されているのです。
>> 【キッカケは2つ】水素水ブームが無くなった理由とは?真実を徹底解説
水素吸入が効果なしのエセ科学と言われる理由②: 前述の通り、水素吸入療法は先進医療として認められていましたが、2022年に取り下げられました。この事実が、「やはり効果がなかったから取り下げられたのだ」という誤解を生み、エセ科学であるという印象 を強めています。
しかし、認定取り下げの主な理由は、COVID-19パンデミックの影響によって臨床試験の継続が困難になったことです。実際、先進医療として実施された臨床試験の結果として、生存率の向上や後遺症の抑制効果を示唆するデータが得られており、「効果がなかったから取り下げられた」のではない ことがわかります。4)
水素吸入が効果なしのエセ科学と言われる理由③: 水素吸入は、現状は保険適用外の自由診療です。このため、「効果がないから保険が適用されないのだ」と考える人もいます。
しかし、保険適用の有無は、治療法の効果だけでなく、費用対効果や普及度、政策的な判断など、様々な要因によって決まります。
先進的な治療法や研究段階の治療法は、必ずしもすぐに保険適用となるわけではありません 。例えば、がんの免疫療法薬『オプジーボ』も、当初は保険適用外でしたが、一部のがん種で保険適用となりました。
したがって、保険適用外であることだけを理由に、水素吸入を「効果がないエセ科学」と断定することはできません。
水素吸入が効果なしのエセ科学と言われる理由④: 一部には、「酸素と水素が結合すれば水になるのだから、水素を吸入しても意味がない」という意見があります。
これは、非常に単純化した化学反応であり、生体内での複雑な相互作用を考慮していません。 吸入された水素分子は、血流に乗って全身に運ばれ、細胞レベルで抗酸化作用や抗炎症作用などの生理活性を示すと報告されています。2)
したがって、単に「水素が酸素と結びついて水になる」という反応だけで、その効果を否定するのは科学的とは言えません。
水素吸入が効果なしのエセ科学と言われる理由⑤: 水素吸入療法は比較的新しい治療法であり、その効果や最適な利用方法については、まだ十分に解明されていない部分があります。特に、長期的な効果や疾患に対する有効性を確立するためには、さらなる研究が必要 です。
また、水素吸入療法は、一般の認知度もまだ低いと言えます。医療従事者の中にも、その効果について誤解や知識不足がある方もおられます。
このような研究の途上段階であることや、認知度の低さが、「効果がないエセ科学」という誤解を生む要因 となっていると考えられます。
水素吸入が効果なしのエセ科学と言われる理由まとめ
水素吸入が「効果のないエセ科学」と言われる理由は、以下の5つに集約されます。
水素水ブームによる悪いイメージ
先進医療からの取り下げによる誤解
保険適用外であることへの誤解
「水素+酸素=水」という化学反応への誤解
研究データの不足と認知度の低さ
しかし、冒頭で述べたように、水素吸入がエセ科学である可能性は極めて低い と言えます。
では、続いて現状水素吸入の効果はどれくらいエビデンスがあるのかについて見ていきましょう。
水素吸入の効果のエビデンスは?どこまで証明されているのか
水素吸入療法の効果や安全性は、研究が進むにつれて徐々に明らかになりつつあります。
ここでは以下について見ていきます。
水素吸入に期待される効果
水素吸入に期待される効果は実に多種多様ですが、その中でも信頼性の高い研究結果があり、特に注目を集めているものを4つご紹介します。
①抗酸化作用・抗炎症作用
水素吸入は、高い抗酸化作用と抗炎症作用を持つことが、多くの研究で示されています。この作用によって、体内の酸化ストレスが軽減され、炎症反応が抑制されると考えられています。
人を対象とした研究はもちろん、ランダム化を用いた信頼性の高い研究でもほとんど一貫した結果 がみられています。
②がん治療
水素吸入が放射線治療や化学療法の副作用を軽減したり、がん患者の生活の質(QOL)を改善したりする可能性が示唆されています。例えば、27件の水素吸入とがん治療に関連する研究報告をまとめた論文では、生存期間の延長や腫瘍マーカーの低下などが報告 されています。5)
がん細胞の縮小なども期待されていますが、現状は抗がん剤や放射線治療の補助療法としてのエビデンスが多く、注目度が高いと言えます。
それぞれについては以下の記事で詳細に解説しているので、ぜひ読んでみてください。【医師監修】水素吸入が放射線治療の副作用を軽減?その可能性と安全性 >> 【医師監修】水素吸入が抗がん剤治療の補助療法として注目される理由
③高血圧
日本人の3人に1人が該当するとされる高血圧に対しても、近年エビデンスが増えてきています。
信頼性の高いランダム化試験や2,000名以上を対象とした観察研究では、水素吸入による降圧効果や標準治療と併用することで治療効果を高めたり、副作用を軽減したりしたことが報告 されています。
水素吸入と高血圧に関するより具体的な研究内容やメカニズムについては、以下の記事で解説しているので、ぜひご参考ください。【医師監修】水素吸入が高血圧の改善に期待される理由とは?最新エビデンスを解説
④認知症
高齢化に伴い今後も患者が増加することが問題視される認知症に対しても、研究報告が増えてきています。
水素分子は非常に小さく、体の隅々にまで行き届くことが報告されています。脳には、血液から入る物質を制限する「血液脳関門」がありますが、水素はこれを突破し、脳の神経細胞を保護する可能性が示唆されています。
実際、認知症の患者を対象とした研究では、脳機能の改善や水素吸入をやめた後も半年以上改善が維持されたことなどが報告 されています。また、標準治療と併用することで治療効果が向上したことも報告されています。【医師監修】認知症と水素吸入の関係とは?予防・改善への可能性を徹底解説
これら4つ以外の疾患や目的に関する水素吸入の効果について解説しているので、ぜひ以下もご参考ください。【疾患・目的別】水素吸入に期待されている効果一覧
水素吸入の安全性やリスク
水素吸入はこれまでの研究において、重篤な副作用は報告されておらず、安全性の高い治療法 として知られています。重篤な副作用とは死亡や障害、入院などを引き起こす副作用のことです。
水素吸入はむしろ、治療薬などの副作用を軽減する可能性が期待されています。
いくつかの研究では、軽い頭痛や吐き気などが見られたと報告されるケースもありますが、いずれも自然に速やかに軽快した と報告されています。【医師監修】水素吸入療法にリスクや副作用はある?各国の規制は?
水素吸入のココがまだ謎!今後取り組むべき5つの課題
様々な効果が期待され安全性が高いとされる水素吸入ですが、実はまだ多くの点が解明されていません。
有効性の確立に向けて、今後の研究では以下のような課題に取り組む必要 があります。
それぞれ解説していきます。
課題①:最適な実施方法の確立
水素吸入を行う上で水素の濃度や吸入量、吸入時間、頻度など、疾患や目的ごとの最適な実施方法(プロトコル)を確立する必要 があります。
これまでの研究は水素濃度や吸入時間などがバラバラであり、水素吸入の効果を最大限得られる標準化された治療方法の解明が求められます。
課題②:長期的な効果の検証
現在の研究の多くは長くても1〜2年の短・中期的な効果を評価したものであり、長期的な安全性や効果については、さらなるデータが必要 です。これは長い年月(5〜10年)をかけて検証していく必要があります。
課題③:作用メカニズムの解明
水素分子は抗酸化作用や抗炎症作用だけではなく、様々なメカニズムによって効果が発揮されていることが報告されていますが、わかっていない部分も多いです。
したがって、体内でどのようなメカニズムで効果を発揮するのか、より詳細な解明 が求められます。
課題④:大規模な臨床試験の実施
より多くの患者を対象とした、質の高いランダム化比較試験(RCT)の実施が求められます。
これまでにもいくつかのRCTは行われていますが、より大規模な試験の実施とそれら複数の研究をまとめる論文(メタ分析)が有効性の確立には必須 です。
課題⑤:個人差の解明
水素吸入に対する反応には個人差があるため、どのような人がより効果を得やすいのか、その要因を明らかにする必要 があります。
今後これらの課題に取り組むことで、水素吸入療法の真の可能性が明らかになれば、より多くの人々がその恩恵を受けられるようになるでしょう。今後の更なる解明に期待しましょう。
水素吸入を試すならクリニックやサロンがおすすめ
水素吸入を試してみようかなと感じられた方は、ぜひ一度お近くの水素吸入サロンやクリニックで試してみて ください。
料金相場は1時間3,000円ほどで、最近はできる施設も増えてきています。
ただし、持病 などで 治療中の方は、必ず主治医に相談の上で実施する ようにしましょう。
水素吸入サロンでの料金や選び方については以下の記事で解説しているので、ご参考ください。水素吸入サロンの料金相場と選び方の6つのポイント
また、お近くの水素吸入サロンを探す場合は、ぜひ以下もご活用ください。【都道府県別】水素吸入ができるサロンとクリニック一覧
効果のない「エセ科学」に騙されないためのリテラシー
水素吸入療法に限らず、世の中には様々な健康法や商品が存在します。「効果のないエセ科学」に騙されないためには、情報リテラシーを身につけることが重要 です。
ここでは、効果のないエセ科学に騙されないための対策についてお伝えします。
「エセ科学」に騙されない対策①: 「科学的根拠(エビデンス)」といえど、これらの中には信頼性の高いものも低いものもあり玉石混合 です。
エビデンスが信頼できるかどうか判断するポイントを以下にまとめてみました。ぜひ参考にしてください。
研究デザイン: ランダム化比較試験(RCT)やメタ分析など、信頼性の高い研究手法かどうかサンプルサイズ: 研究に参加した人数が十分に多いかどうか対照群の有無: プラセボ(偽薬)を用いた対照群が設定されているかどうか盲検化: 研究者と参加者の両方が、どちらの治療を受けているかを知らない盲検化が行われているか査読の有無: 研究論文が、専門家による査読を受けている学術雑誌に掲載されているか複数の研究結果: 一つの研究結果だけでなく、複数の研究で同様の結果が得られているかどうか情報源の信頼性: 情報の発信元が信頼できる機関や専門家であるか
こういったエビデンスの読み方については、以下の書籍が大変わかりやすく勉強になるので、ぜひこちらもご参考ください。
書籍:心理職のためのエビデンス・ベイスト・プラクティス入門―エビデンスを「まなぶ」「つくる」「つかう」
「エセ科学」に騙されない対策②: 自分でエビデンスの信頼性の判断が難しい場合は、専門家の意見を尋ねるのも有効な方法の1つ です。
かかりつけ医はもちろん、その分野に詳しい専門医や、資格を持った医療従事者(管理栄養士、薬剤師など)に相談することで、正しい情報を得ることができます。
信頼できる相談先としては、医療機関、専門学会のウェブサイト、公的機関の相談窓口などが挙げられます。
1人の専門家や1つの情報源だけではなく、複数から聞いたり集めたりするとより効果的 です。
新しい健康法を試す前に!必ず確認すべきチェックリスト
最後に、今後何か新しい健康法を知った際に確認すべき具体的なポイントをお伝えします。
ぜひ、信頼できる情報かどうか確認する際にご活用ください。
その健康法の情報源は信頼できるか?(誰が、なぜ情報を発信している?)
科学的根拠はあるか?対策①:科学的根拠(エビデンス)を正しく見極める 」を参照)
誇大広告や「〇〇するだけで治る!」といった安易な表現はないか?
リスクや副作用はないか?
費用は高額ではないか?
自分の健康状態や目的に合っているか?
専門家(医師など)はなんと言っているか?
これらの点を確認することで、効果のないエセ科学に騙されるリスクを減らす ことができます。
効果のないエセ科学に騙されて多額のお金を投じたり、ましてや健康を害してしまわないように、ぜひこれらのチェックリストをご活用ください。賢く選択して、健康への投資を成功させましょう。
まとめ:水素吸入は「効果なしのエセ科学」ではなく期待が集まる治療法
今回は、水素吸入療法が効果のない「エセ科学」なのかどうかについて、科学的根拠に基づいて検証しました。結論として、水素吸入療法は、過去に厚生労働省に先進医療として認められた実績があり、現在も国内外で臨床研究が進められている「科学的に解明が進んでいる治療法」といえます。これまでの研究では、高血圧や認知症、がんなどに対する潜在的な効果が示唆されており、決して「効果がないエセ科学」と断言できるものではありません。
しかし、過去の水素水ブームの影響や、先進医療認定の取り下げ、保険適用外であることなどから、「効果がないエセ科学」という誤解が生じていることも事実です。また、研究がまだ途上段階であり、最適なプロトコルや長期的な効果については、さらなる解明が必要です。
水素吸入療法を検討する際には、医師やその他の専門家に相談のうえ、自身の健康状態や目的に合わせて慎重に判断することが大切です。今後の研究の進展により、水素吸入療法がより効果的な健康法として確立されることを期待しましょう。
参考文献
Ohsawa, I., Ishikawa, M., Takahashi, K., Watanabe, M., Nishimaki, K., Yamagata, K., Katsura, K., Katayama, Y., Asoh, S., & Ohta, S. (2007). Hydrogen acts as a therapeutic antioxidant by selectively reducing cytotoxic oxygen radicals. Nature medicine , 13 (6), 688–694. https://doi.org/10.1038/nm1577
太田成男 (2015). 水素医学の創始,展開,今後の可能性:広範な疾患に対する分子状水素の予防ならびに治療の臨床応用へ向かって. 生化学, 87(1), 82-90. doi:10.14952/SEIKAGAKU.2015.870082 Dong, G., Wu, J., Hong, Y., Li, Q., Liu, M., Jiang, G., Bao, D., Manor, B., & Zhou, J. (2024). Inhalation of Hydrogen-rich Gas before Acute Exercise Alleviates Exercise Fatigue: A Randomized Crossover Study. International journal of sports medicine , 45 (13), 1014–1022. https://doi.org/10.1055/a-2318-1880
Tamura, T., Suzuki, M., Homma, K., Sano, M., & HYBRID II Study Group (2023). Efficacy of inhaled hydrogen on neurological outcome following brain ischaemia during post-cardiac arrest care (HYBRID II): a multi-centre, randomised, double-blind, placebo-controlled trial. EClinicalMedicine , 58 , 101907. https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2023.101907
Mohd Noor, M. N. Z., Alauddin, A. S., Wong, Y. H., Looi, C. Y., Wong, E. H., Madhavan, P., & Yeong, C. H. (2023). A Systematic Review of Molecular Hydrogen Therapy in Cancer Management. Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP, 24(1), 37–47. https://doi.org/10.31557/APJCP.2023.24.1.37