春の不調の原因「黄砂」の正体と健康リスク

春になると日本に飛来する「黄砂」。これは、中国内陸部の砂漠地帯(ゴビ砂漠など)で強風により舞い上がった土壌粒子が、偏西風に乗って運ばれてくる現象です。
これを単なる砂と侮ってはいけません。その正体と、私たちの体に及ぼすリスクを見ていきましょう。
黄砂のピークはいつ?影響を受けやすいのは?
日本で黄砂の飛来がピークを迎えるのは、主に3月から5月の春先です。1)この時期は、発生源である砂漠地帯の乾燥や、日本へ向かう強い西風といった気象条件が重なるためです。
特に、地理的に発生源に近い西日本や九州地方では、黄砂の影響がより顕著になる傾向があります。また、この時期は花粉の飛散シーズンとも重なるため、アレルギー症状などがより複雑になったり、悪化したりする一因とも考えられています。
ただの砂じゃない!黄砂に含まれる有害物質のリスク
「黄砂って、ただの砂でしょ?」と思うかもしれませんが、実はそうではありません。黄砂の粒子は非常に小さく(直径わずか4μm程度。1μmは1mmの1000分の1)、その広い表面には様々な物質が付着しやすい性質を持っています。
そのため、黄砂が長い距離を飛んでくる間に、PM2.5(微小粒子状物質)や細菌、カビ、大気中の化学物質といった有害物質を吸着してしまいます。まるで汚れたスポンジのように、これらをくっつけて日本まで運んできてしまうのです。
これらの有害物質を含んだ黄砂が体内に入ると、体の防御システムが過剰に反応し、「炎症」や「酸化ストレス」(※後述)を引き起こし、健康被害を招くと考えられています。
鼻水、咳、肌荒れ…黄砂による代表的な症状
黄砂の飛来に伴って、多くの方が様々な症状を経験します。主にアレルギー症状や呼吸器系の症状が顕著に現れます。
より具体的な黄砂による症状は以下のようなものです。
黄砂の濃度が高い日ほど、これらの症状を発症する方が多くなる傾向があります。1)特に小児や高齢者、既存の呼吸器疾患を持つ方は注意が必要です。
「水素吸入」って何?期待される効果とは

水素吸入とは、分子状の水素(H₂)を含む空気を吸入する健康法です。
近年、様々な研究から、この水素に「抗酸化作用」と「抗炎症作用」があることが分かり、医療や健康分野で注目されています。2)
私たちの体の中では、呼吸などによって「活性酸素」が常に作られています。これには体を守る「善玉」もいますが、ストレスや大気汚染などで「悪玉」が増えすぎると、細胞がサビつくようにダメージを受け(=酸化ストレス)、老化や不調の原因になります。また、体の一部で続く慢性的な「炎症」も、様々な問題を引き起こすことが知られています。
水素は、特に有害な悪玉活性酸素を選択的に除去したり、過剰な炎症を抑えたりする働きを持つことが報告されています。これらの問題を軽減することで、私たちの健康維持に役立つ可能性があると考えられているのです。
>> 水素吸入療法の効果や副作用は?知っておきたい基礎知識まとめ
水素吸入は黄砂による不調の改善に役立つ?

現時点では、正直なところ、黄砂への直接効果を示す研究はまだ多くありません。 しかし、黄砂ダメージの原因「体のサビ(酸化ストレス)」や「炎症」への効果が期待されています。
ここでは、関連する症状(鼻炎や咳など)の研究から、その可能性を見ていきましょう。
黄砂ダメージの元凶「酸化ストレス」と「炎症」
黄砂が体に及ぼす悪影響の主な原因は、「体のサビ(酸化ストレス)」と「炎症」です。
有害物質を含んだ黄砂が体内に入ると免疫細胞などが反応し、悪玉活性酸素が過剰に発生します。これが「酸化ストレス」です。
さらに、体は異物やダメージに対抗しようとして、「炎症」という反応を起こします。これが鼻で起これば鼻炎、気道なら咳や喘息、皮膚なら皮膚炎につながります。
黄砂による不調の多くは、こうした「酸化ストレス」と「炎症」が根本的な原因となっていると考えられます。
水素の「抗酸化・抗炎症作用」が役立つ可能性
ここで、先ほど説明した水素の力が関係してきます。
水素には、増えすぎた悪玉活性酸素(体のサビ)を選択的に減らす「抗酸化作用」と、体の「火事(炎症)」を鎮める「抗炎症作用」が期待されています。
つまり、水素は黄砂ダメージの根本原因にアプローチできるかもしれない、ということです。
具体的にどんな効果が期待できる?研究データを紐解く
この働きから、以下のような症状への効果が期待され、研究報告も出てきています。
それぞれ解説していきます。
アレルギー症状の緩和(鼻炎など)
アレルギー性鼻炎では、水素吸入でくしゃみ・鼻水といった症状や、体内の炎症を示す指標が改善したとの報告があります3)
これは水素の抗炎症作用が、つらい鼻炎症状の緩和に役立つ可能性を示唆しています。
参考:アレルギー性鼻炎の予防と改善に水素吸入!最新研究をもとに解説
呼吸器系の負担軽減(COPDなど)
慢性閉塞性肺疾患(COPD)や喘息では、水素吸入により体内の炎症レベル低下や、息切れ・咳・痰といった症状の改善が報告されました。4,5)
黄砂で悪化しやすい呼吸器系の負担を、水素が和らげる可能性が考えられます。
参考:500万人が苦しむCOPDに水素吸入が効果あり?最新研究をもとに解説
参考:水素吸入療法は喘息の予防や改善に役立つ?
そのほかの症状(頭痛や倦怠感など)
慢性疲労症候群に伴う頭痛や倦怠感も、水素吸入によって軽減したという報告があります。6)
酸化ストレスや炎症が関わる、黄砂による全身的な不調に対しても改善が期待できるかもしれません。
参考:水素吸入療法は頭痛の予防や改善に役立つ?
参考:水素吸入で疲労回復?運動後の疲労や慢性疲労への効果を徹底解説
水素吸入は黄砂による不調の改善に役立つ可能性まとめ
水素吸入と黄砂による不調のまとめは以下のとおりです。
- 黄砂への直接効果は研究中。
- 原因となる「体のサビ」や「炎症」への効果に期待。
- 鼻炎や呼吸器症状など、関連症状での良い研究報告はある。
現時点では「可能性」の段階ですが、体の内側からケアする新しい選択肢として、従来の対策(マスクなど)と組み合わせる価値はあるかもしれません。
水素吸入を行う方法とその際の注意点

「水素吸入、ちょっと試してみたいかも…」と思った方へ向けて、実際に始めるにはどうすれば良いのか、そして注意すべき点について説明します。
水素吸入を行う方法は2通り
水素吸入を始める方法は、主に「① サロンやクリニックで体験する」方法と「② 自宅に吸入器を導入する」方法があります。
サロンやクリニックでは専門機器で手軽に試せますが、通う手間や継続的な費用がかかる場合があります。一方、自宅用は好きな時に使えますが、初期費用や機器の自己管理が必要です。
どちらが良いかはライフスタイルや予算によりますが、まずはサロン等で一度体験してみるのがおすすめです。
それぞれの詳細なメリット・デメリットや料金相場、機器の選び方は、以下の記事をご覧ください。
>> 水素吸入サロンの「料金相場」は1時間3000円!プランと選び方を解説
>> 失敗しない水素吸入器の選び方|9つのポイント解説
水素吸入を行う際の注意点
水素吸入は一般的に安全性が高いとされていますが、以下の点に注意が必要です。
- 安全性と副作用について:水素吸入療法は、多くの臨床試験において重大な副作用はほとんど報告されていませんが、稀に軽微な副作用として吐き気や気分不良、頻尿、催眠などが報告される場合があります。
- 適切な機器の選択と管理:高濃度の水素ガスは可燃性であるため、安全な装置を使用し、適切な管理のもとで行う必要があります。メーカーのガイドラインや説明書をよく読み、指示に従って使用しましょう。
- 医療従事者への相談:持病がある方や妊娠中・授乳中の方は、水素吸入を始める前に医師に相談するようにしましょう。
- 医療行為ではないこと:水素吸入は、病気の治療を目的とした医療行為ではありません。あくまで健康維持やコンディショニング、セルフケアの一環として捉えましょう。
- 過度な期待を持たないこと:水素吸入は医療行為ではなく、効果の感じ方には個人差があります。現時点では黄砂対策としての有効性を直接示す十分な科学的根拠はまだ確立されておらず、あくまで可能性の段階であることを理解しておくことが大切です。
これらの注意点をしっかりと把握し、黄砂対策の一環として水素吸入をうまく活用していきましょう。
水素吸入だけじゃない!黄砂シーズンを乗り切るための対策3選

水素吸入は黄砂対策の一つの選択肢ですが、それだけに頼るのではなく、複合的なアプローチを取ることが重要です。
ここでは、水素吸入以外に取り組める「より効果的に黄砂シーズンを乗り切る」ための対策を3つご紹介します。
- 黄砂を徹底ブロック(マスク・メガネ・空気清浄機)
- 帰宅後のひと工夫(うがい・洗顔・衣類のケア)
- 体の内側からバリア強化(食事・睡眠・腸内環境)
それぞれ解説します。
黄砂対策①:黄砂を徹底ブロック(マスク・メガネ・空気清浄機)
まずは、黄砂を体内に取り込まないための「物理的な防御」が最も重要です。
物理的な防御のポイントは以下のとおりです。
マスクを着用する
黄砂の飛来が多い日は、顔にしっかりフィットする高機能なマスク(不織布製、できればPM2.5対応やN95/KF94規格など)を着用しましょう。鼻やあご周りに隙間ができないように、正しく着けることがポイントです。
メガネ・ゴーグルを活用する
目のかゆみが気になる方は、通常のメガネや、花粉対策用のゴーグルを使用すると、目に入る黄砂の量を減らせます。コンタクトレンズの方は特に意識しましょう。
空気清浄機を使う
室内では、HEPAフィルターなど、細かい粒子を捕集できる高性能なフィルターを搭載した空気清浄機を活用しましょう。窓際はもちろん、人が長く過ごすリビングや寝室に置くと効果的です。フィルターの定期的な掃除や交換も忘れずに。
黄砂対策②:帰宅後のひと工夫(うがい・洗顔・衣類のケア)
外出先で体に付着した黄砂を、家の中に持ち込まない、残さない工夫も大切です。
そのために以下のポイントを意識しましょう。
うがい・手洗い
帰宅したら、すぐにうがいと手洗いを習慣にしましょう。喉の奥や鼻の粘膜についた黄砂を洗い流すイメージで。可能であれば「鼻うがい」も効果的です。
洗顔・洗髪
顔や髪にも黄砂は付着します。帰宅後、早めに洗顔し、できればシャワーを浴びて髪も洗い流すと、よりスッキリします。
衣類のケア
玄関に入る前に、衣類についた黄砂を軽く払い落としましょう。黄砂が多い日は、洗濯物は外に干さず、室内干しにするのがおすすめです。
黄砂対策③:体の内側からバリア強化(食事・睡眠・腸内環境)
体の防御力を高め、黄砂に負けない体作りも大切です。
基本的な内容ですが、改めて日々実践できているか確認してみましょう。
バランスの取れた食事
粘膜を保護するビタミンA(緑黄色野菜、レバーなど)、抗酸化作用のあるビタミンC(果物、野菜)やビタミンE(ナッツ、植物油)、免疫に関わるビタミンD(魚、きのこ、日光浴)などを意識的に摂りましょう。また、ポリフェノール(野菜、果物、お茶など)も抗酸化に役立ちます。
腸内環境を整える
腸は最大の免疫器官とも言われます。ヨーグルトなどの発酵食品や、食物繊維(野菜、海藻、きのこ)を積極的に摂り、腸内環境を整えましょう。
質の高い睡眠
十分な睡眠時間を確保し、寝る前のスマホを控えるなどして睡眠の質を高めることも、免疫機能を維持するために大切です。
黄砂対策おまけ:水素吸入と組み合わせる
基本的な対策(物理的防御、帰宅後のケア、体内バリア強化)をしっかり行った上で、水素吸入をプラスする。この「複合的なアプローチ」こそが、黄砂シーズンを乗り切るための賢い戦略と言えるでしょう。
基本的な対策(物理的防御、帰宅後のケア、体内バリア強化)をしても体内に入ってしまった黄砂によるダメージ(酸化ストレスや炎症)を「内側からケア・リカバリーする(修復・鎮静)」という役割が期待できるかもしれません。
水素吸入は魔法の解決策ではありませんが、従来の対策を補完する「プラスアルファの選択肢」として取り入れていくのが良いでしょう。
まとめ:黄砂対策としての「水素吸入」の可能性と賢い付き合い方
今回は、春先の悩みの種である「黄砂」と、その対策として注目される「水素吸入」について、詳しく解説してきました。
黄砂は単なる砂ではなく、様々な有害物質を含む複合的な環境因子であり、呼吸器系の症状、アレルギー症状、全身の不調など、様々な健康問題を引き起こす可能性があります。
水素の持つ抗酸化作用と抗炎症作用が、黄砂によって引き起こされる酸化ストレスや炎症を軽減する可能性があります。ただし、現時点では黄砂対策としての水素吸入の効果を直接的に検証した臨床試験はまだ十分ではなく、あくまで可能性の段階と言えます。
黄砂の季節は辛いものですが、正しい知識と適切な対策で、その影響を最小限に抑えることができます。水素吸入は新たな可能性を秘めた選択肢の一つとして、他の対策と組み合わせながら、賢く活用していくことが望ましいでしょう。
最後に、健康上の懸念がある場合は、必ず医療専門家に相談することをお勧めします。最新の研究成果にも注目しながら、自分に合った黄砂対策を見つけていきましょう。
参考文献
- 黄砂とその健康影響について(2019年3月発行)|環境省
- Ge, L., Yang, M., Yang, N. N., Yin, X. X., & Song, W. G. (2017). Molecular hydrogen: a preventive and therapeutic medical gas for various diseases. Oncotarget, 8(60), 102653–102673. https://doi.org/10.18632/oncotarget.21130
- Wang, N., Ma, Q., Zhai, J., Che, Y., Liu, J., Tang, T., Sun, Y., Wang, J., & Yang, W. (2024). Hydrogen inhalation: A novel approach to alleviating allergic rhinitis symptoms by modulating nasal flora. The World Allergy Organization journal, 17(10), 100970. https://doi.org/10.1016/j.waojou.2024.100970
- Wang, S. T., Bao, C., He, Y., Tian, X., Yang, Y., Zhang, T., & Xu, K. F. (2020). Hydrogen gas (XEN) inhalation ameliorates airway inflammation in asthma and COPD patients. QJM : monthly journal of the Association of Physicians, 113(12), 870–875. https://doi.org/10.1093/qjmed/hcaa164
- Zheng, Z. G., Sun, W. Z., Hu, J. Y., Jie, Z. J., Xu, J. F., Cao, J., Song, Y. L., Wang, C. H., Wang, J., Zhao, H., Guo, Z. L., & Zhong, N. S. (2021). Hydrogen/oxygen therapy for the treatment of an acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease: results of a multicenter, randomized, double-blind, parallel-group controlled trial. Respiratory research, 22(1), 149. https://doi.org/10.1186/s12931-021-01740-w
- Hirano, S., Ichikawa, Y., Sato, B., Takefuji, Y., & Satoh, F. (2024). Successful treatment of myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome using hydrogen gas: Four case reports. Medical Gas Research, 14(2), 84-86. https://doi.org/10.4103/2045-9912.385441
このコラム記事は、一般的な医学的情報および最新の研究動向をもとに作成しておりますが、読者の方の個別の症状や体質などを考慮したものではありません。また、医学的アドバイス、診断、治療に代わるものではなく、特定の製品や治療法の効果・効能を保証、証明するものでもありません。健康上の問題がある場合は、自己判断せずに医療機関を受診し、医師などの専門家に必ずご相談ください。本コラム記事の情報をもとに被ったいかなる損害についても、当方は一切の責任を負いかねます。
※本記事は、公開時点での情報に基づいて作成しており、最新のものと異なる場合があります。予めご了承ください。

本記事は医療健康情報を含むコンテンツを専門医が確認する「メディコレWEB」の認証を受けています。
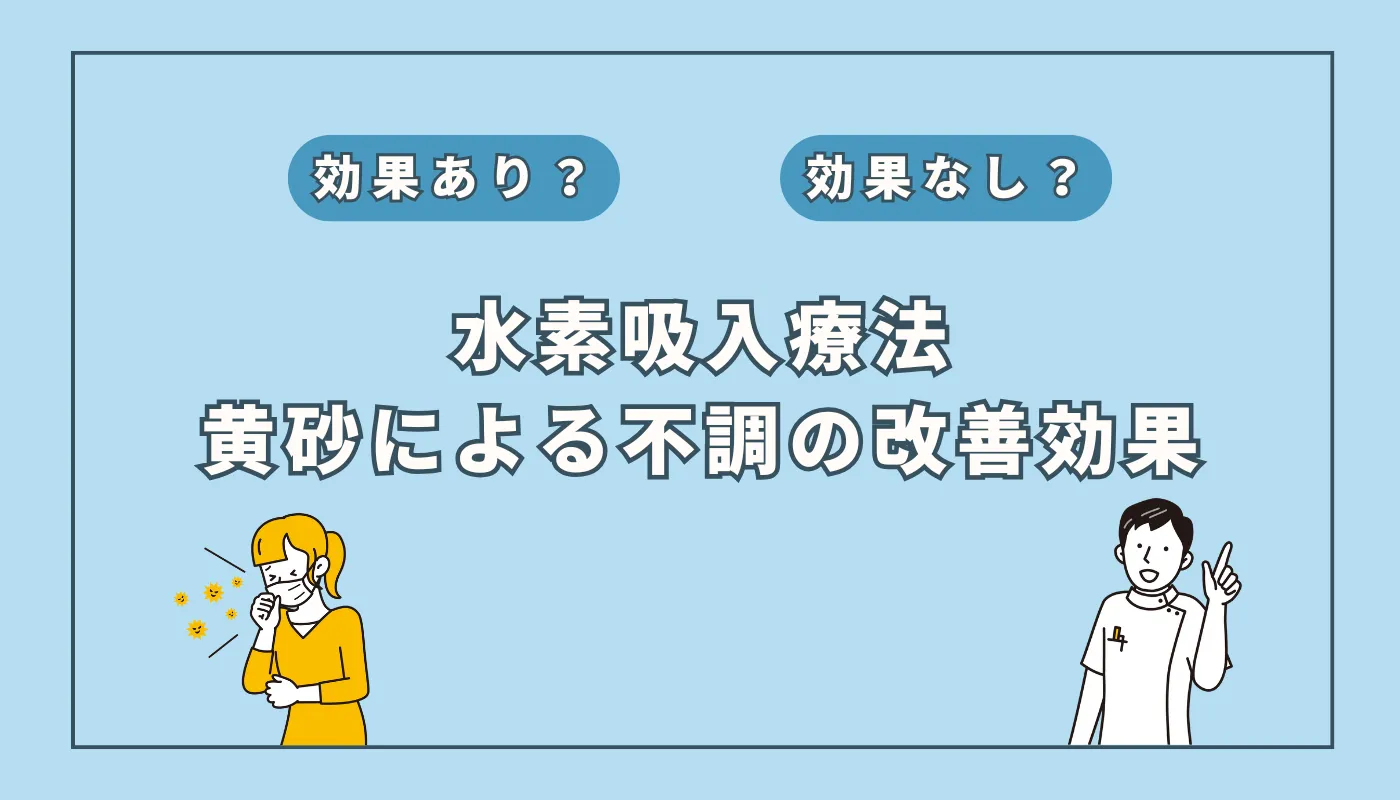
医師
本多洋介 先生
水素療法がこれまでに示してきた「抗酸化作用」と「抗炎症作用」がアレルギー性鼻炎や喘息に対しても効果があることから、黄砂による体の不調に対しても効果が期待できそうです。黄砂による症状は既存の治療でも対応が難しいため、症状が残存している方は水素療法との併用にトライしてみてはいかがでしょうか。