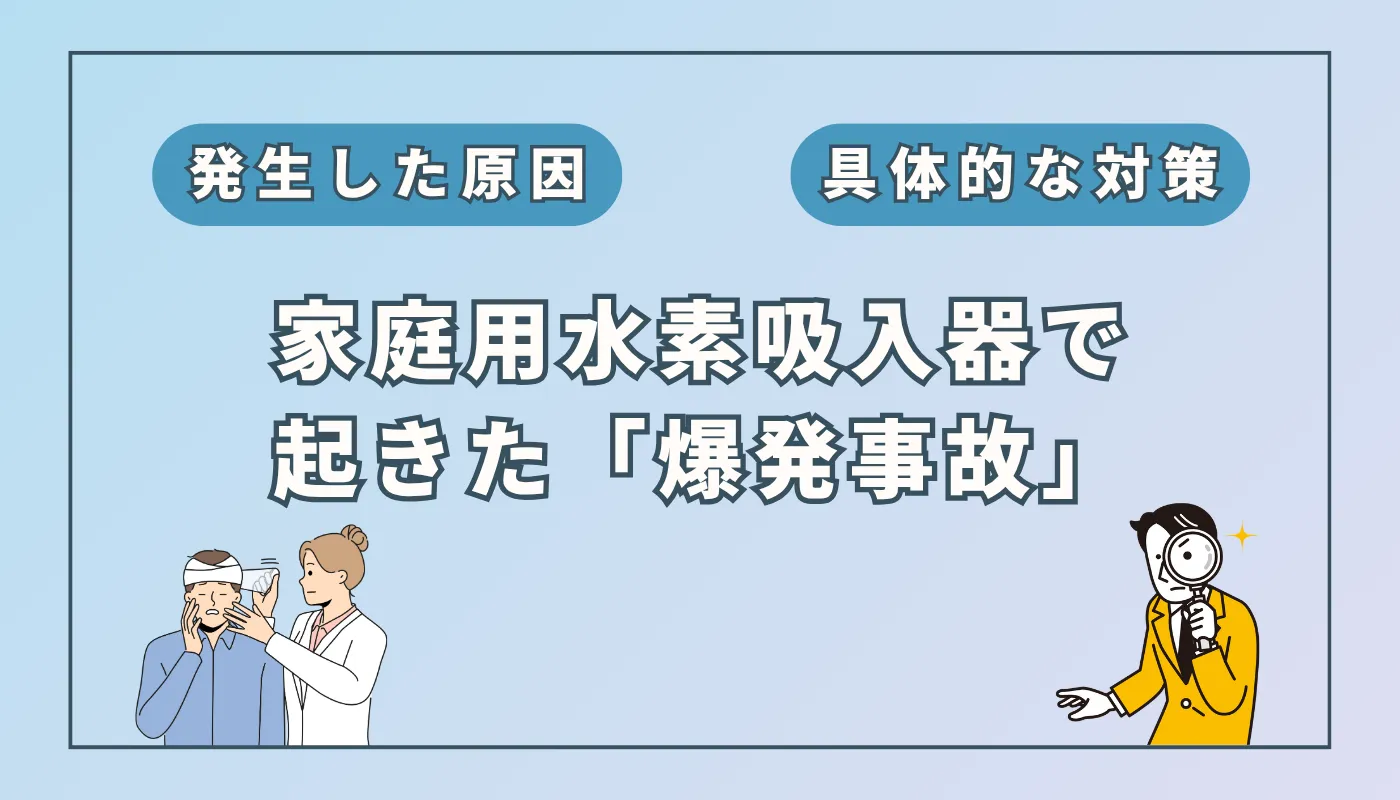「水素吸入器が爆発した」というニュースを聞いて、不安を感じている方もいらっしゃるかもしれません。
利用中の方はもちろん、導入を検討している方にとっても、非常に気がかりな情報だと思います。
当サイトでは、この件を慎重に扱うべきと考え、これまでこの話題をあえて控えてきました。しかし、水素吸入の健全な普及と、何よりも利用者の皆様の安全を第一に考え、実際に起きた事故の事例を正確にお伝えし、そこから得られる教訓を共有すべきだと判断いたしました。
この記事では、家庭用水素吸入器の使用中に起きた爆発事故の原因と、そこから学ぶ爆発させないための具体的な対策についてお伝えします。
当記事内では、爆発事故を起こした機器や企業名の掲載は控えます。
家庭用水素吸入器で起きた「爆発事故」の概要

まず、どのような事故だったのか、公表されている情報に基づき概要を整理します。
この事故は2024年の初め頃に発生しました。報告によれば、利用者が家庭用水素吸入器を使用中、機器の外付けボトルから「異音」がした直後、鼻の内部で軽爆発が発生。その結果、鼻骨骨折およびヤケドを負うという重大な事故に至りました。
同事故は、消費者庁にも報告されています。
水素ガスは、一定の条件が揃うと引火・爆発する可能性がある可燃性ガスです。この事例は、通常の使用環境下であっても、特定の条件が重なることで事故に至る危険性があることを示したと言えます。
>> 水素吸入で水素爆発する「条件3つ」
事故から判明した「爆発のメカニズム」
なぜ、通常の使用中に鼻腔で爆発が起きてしまったのでしょうか。
事故調査から推測されるメカニズムは、大きく分けて「ガスの充満」と「発火源」という2つの要因が重なったことでした。
要因①:カニューレの閉塞による「ガス充満」

まず、水素ガスが管内に滞留し、局所的に水素濃度が高くなったことが一因として挙げられます。
事故調査によれば、使用中にカニューレや接続管が折れたり潰れたりしたことでガスが滞留。その後、管内の圧力を解消するために外付けボトル※の安全弁が作動しました。その際の異音に利用者が驚いて動いたことで管の閉塞が解消され、溜まっていた水素ガスがカニューレ先端から一気に放出されました。
その結果、鼻腔周辺の空気中の水素濃度が急激に高まったと考えられます。
※外付けボトルは、水素ガスから水分を除去するためのものです。機器から出たガスを、ボトル内の水の中に一度通すことで水分を取り除きます。
要因②:身体に帯電していた「静電気」による引火

もう1つの要因は、身体に帯電していた静電気です。
利用者の身体に帯電していた静電気が火種(発火源)となり、上述した理由によって一気に放出された水素ガスに引火。鼻腔内という狭い空間で軽爆発を引き起こしてしまったと考えられます。実際にどの程度の爆発が起こったかについては不明ですが、鼻骨骨折をする程度の衝撃はあったと推測されます。
このように、この事故は「管の閉塞によるガスの充満」と「静電気という発火源」という、日常に潜む2つのリスクが不運にも重なったことで発生したと言えます。
事故から学ぶ「今日から実践すべき安全対策」

今回の事故は非常に痛ましいものですが、裏を返せば、原因が特定できているため「対策が可能」であるとも言えます。
ここでは、この事例から学ぶ、私たちが今日から実践すべき3つの対策を解説します。
爆発対策①:使用中の「管の折れ・潰れ」の防止
まずは、「管(カニューレ)の管理」をしっかりと行いましょう。
使用中は、カニューレや接続管などの管が折れたり、潰れたりしないよう、細心の注意を払ってください。管内にガスが充満し、一気に放出されることは、今回の事故が示す通り爆発を招く危険があります。
特に、寝転がりながら使用する際や、柔らかいシリコン製のカニューレを使用している場合は、身体の下敷きになって管が潰れたり、折れ曲がりやすくなるため注意が必要です。
対策として、あえて少し硬さのある「ポリ塩化ビニル(PVC)」素材のカニューレを選ぶのも一つの手です。
一部製品では、「ノンクラッシュチューブ」と言って、折れ曲がっても閉塞しにくい仕組みのカニューレもあります。(アトム酸素鼻孔カニューラ )
爆発対策②:「静電気」の除去を習慣化
今回の事故で、ライターなどの「火気」だけでなく、「静電気」も発火源になり得ることが示されました。
水素吸入器を使用する際、特に冬場など乾燥した時期には、静電気対策を徹底する必要があります。
静電気は無意識のうちに身体や衣服に溜まってしまうので、以下の対策を実践しましょう。
- 壁や金属製のドアノブに触れ、身体の静電気を放電(静電気除去パッドも有効)
- 加湿器で部屋の湿度を適切に保つ
(乾燥は静電気の最大の原因)
- 除電機能付きの空気清浄機を活用し、静電気を抑制(例:SHARPプラズマクラスター)
- 静電気除去マットを機器の下や自身の足元に設置
特に、部屋の乾燥は静電気だけではなく感染症リスクや肌荒れ・喉の痛みなどにもつながるので、加湿器の活用はおすすめです。また、静電気除去パッドを壁や机の上など触れやすい場所に設置し、水素吸入前に一度触れて静電気を逃がしておくことも効果的です。
爆発対策③:基本の「火気厳禁」と「十分な換気」を徹底
水素吸入における最も基本的な安全ルールを再確認し、必ず実践するようにしましょう。
まずは、水素吸入器の使用中にライターやタバコ、ガスコンロ、ストーブ等の火器類は絶対に使用しないでください 。これは自分から爆発を招く行為であり、大変危険です。
また、使用中の換気も徹底しましょう。水素ガスは空気より軽いため、室内に滞留しづらいとされますが、必ず風通しの良い場所で使用してください。密閉された空間(換気扇を止めた狭い部屋など)での使用は避けましょう。
実際に、機器の使用中にガス検知・警報器が作動する事例も報告されています。リビングなどで使用する場合も、部屋のドアを少し開けておくなど、空気の通り道を確保しましょう。
事故を防ぐ「安全な水素吸入器」選びの視点

もし、これから水素吸入器の購入やレンタルを検討されている方は、「安全対策」が施された機器を選ぶことも重要です。
今回の事故では、ガスの滞留が大きな要因の1つでした。こうした使用中の異常が発生した際に、機器側で安全を確保する機能(防爆機能、内部での水素漏れや異常を検知した際の自動停止機能など)が搭載されているかは、爆発を防ぐための重要なポイントとなります。爆発リスクを少しでも下げるために、しっかりと確認しておきましょう。
そのほか見ておくべき「安全性」の重要ポイントについては、以下の記事で詳しく解説していますので、併せてご参考ください。
まとめ:爆発事故は「知識」と「ひと手間」で防げる
家庭用水素吸入器の爆発事故という報告は、非常に衝撃的で不安を感じるものだと思います。
しかし、その原因を詳しく見ていくと、「管の折れ曲がり(閉塞)」と「静電気」という、非常に具体的で、かつ日常生活の中で対策可能な要因が重なって起きたことが分かりました。
これらのリスクは、日々の「ひと手間」――すなわち、管の状態を管理すること、静電気を除去すること、換気を行うこと――で、そのほとんどを防ぐことができます。
これからも安全を第一に正しい利用法を守り、水素を上手に活用していきましょう。