2型糖尿病とは?原因や症状、治療法

2型糖尿病は、血糖値を下げるホルモン「インスリン」が十分に働かなくなる病気です。
体内でインスリンの効きが悪くなる(インスリン抵抗性)ことと、膵臓からのインスリン分泌が減ることで、血液中の糖(血糖)が高い状態が続きます。
2型糖尿病は、日本の糖尿病患者さんの約90%を占める最も一般的なタイプです。
令和5年の『国民健康・栄養調査』によると、20歳以上で「糖尿病が強く疑われる者」の割合は男性で16.8%、女性で8.9%と報告されています。これは男性の約6人に1人、女性の約11人に1人が該当する計算になります。1)
1型糖尿病との違い
同じ糖尿病という名前ですが、1型糖尿病と2型糖尿病は病態や原因、治療法などが大きく異なります。
主な違いは以下の通りです。
| 1型糖尿病 | 2型糖尿病 | |
| 主な原因 | 自己免疫などでインスリン工場(膵臓β細胞)が壊れる | 遺伝的要因 + 生活習慣(食べ過ぎ・運動不足など) |
| インスリン | 工場が壊れ、ほとんど作られない | 作る量が減る/うまく効かなくなる(インスリン抵抗性) |
| 生活習慣との関係 | あまり関係ない | 関係が大きい |
| 主な治療 | インスリン注射(必須) | 生活習慣の改善、飲み薬、インスリン注射など |
簡単に言うと、1型は「インスリンを作る工場(膵臓)が壊れてしまった状態」、2型は「インスリン工場は動いているが生産量が落ちたり、インスリンがうまく働けなくなったりした状態」と例えられます。日本人の糖尿病患者さんの多くが、主に生活習慣に起因する2型糖尿病とされます。
1型糖尿病について詳しくは以下で解説しています。
>> 【医師監修】水素吸入は1型糖尿病の補助療法になる?研究から見える可能性
2型糖尿病の主な原因
2型糖尿病の発症には、遺伝的な要因(体質)と環境的な要因(生活習慣)の両方が関わっています。
特に日々の生活習慣が大きく関わっていることからも、2型糖尿病は「生活習慣病」の1つとされています。
具体的に以下のような生活習慣が2型糖尿病の要因として挙げられます。
- 食べ過ぎ・飲みすぎ:高カロリー・高脂肪な食事、糖分の多い飲料の過剰摂取。
- 運動不足:エネルギー消費量が少なく、インスリンの効きが悪くなりやすいとされます。
- 肥満(特に内臓脂肪型肥満):内臓脂肪から分泌される物質がインスリンの働きを妨げます。
- ストレス:ストレスホルモンが血糖値を上げる作用を持ちます。
- 加齢:年齢とともにインスリンの分泌量が減ったり、効きが悪くなったりする傾向があります。
- 他の病気や薬の影響:特定の病気(膵臓疾患など)や薬(ステロイドなど)が原因となることもあります。
こうした生活習慣に加えて、家族や親戚に糖尿病の方がいる場合、糖尿病になりやすい体質を受け継ぐ遺伝的要因もあります。
これらの要因が重なると、筋肉や肝臓でインスリンの効きが悪くなり、同時に膵臓の負担が増してインスリン分泌も低下します。その結果、血糖値が上がり続ける悪循環に陥ります。
特に日本では、食生活の変化により糖尿病患者数が年々増加しており、40代以降の中高年を中心に「沈黙のパンデミック」とも呼ばれています。また、糖尿病と診断された人の約4人に1人は治療を受けていないとされており、早期発見と適切な治療の開始が課題となっています。2)
2型糖尿病の主な症状と合併症
2型糖尿病は初期には自覚症状がほとんどないため「サイレントキラー(静かな殺し屋)」とも呼ばれます。
しかし血糖値が高い状態が続くと、次のような症状が現れてきます。
- 喉が渇く、水をよく飲む(多飲)
- トイレが近くなる(多尿)
- 疲れやすい、だるさを感じる(倦怠感)
- 体重が減少する
- 傷が治りにくい
- 視力の変化
さらに長期間血糖値が高い状態が続くと、体のさまざまな部分に合併症を引き起こします。
- 目の障害:糖尿病網膜症(最悪の場合、失明につながる)
- 腎臓の障害:糖尿病腎症(透析が必要になることも)
- 神経の障害:糖尿病神経障害(しびれ、痛み、感覚異常など)
- 大きな血管の障害:心筋梗塞、脳卒中
- その他:感染症にかかりやすくなる、歯周病、がんリスクの上昇
また、2型糖尿病の人は高血圧や脂質異常症(コレステロール異常)を併発することが多く、これらが重なると動脈硬化が急速に進行するリスクが高まります。
2型糖尿病の治療法
2型糖尿病の治療の基本は「生活習慣の改善」です。バランスの良い食事や総カロリーの適正化などの「食事療法」やウォーキングや筋トレを定期的に行うようにする「運動療法」などを通じて、インスリン抵抗性の改善を目指します。
これらの基本療法だけで血糖コントロールが難しい場合は、以下のような薬物療法が追加されます。
- メトホルミン:肝臓での糖の生産を抑える
- DPP-4阻害薬:インスリン分泌を促進し、食後の血糖上昇を抑える
- SGLT2阻害薬:尿から糖を排出する
- スルホニル尿素薬:インスリン分泌を促進する
- インスリン注射:不足しているインスリンを補充する
- GLP-1受容体作動薬:インスリン分泌を促し、食欲を抑える
近年は連続血糖測定器(CGM)や膵島移植などの新しい技術も登場していますが、根本的な「治る治療法」はまだなく、生涯にわたる血糖コントロールが重要です。そのような状況の中、新しい治療法の開発のため様々な研究が今でも進められており、水素吸入療法もそのうちの1つです。
臨床研究からみる水素吸入の2型糖尿病への有効性
「水素吸入療法」とは、その名の通り水素ガスを吸うことで体内に水素を取り込む治療法です。水素は体内の有害な活性酸素だけを選んで除去する「選択的抗酸化作用」があることが2007年に発見され、それ以来、さまざまな病気への応用が研究されてきました。3)
近年、2型糖尿病治療の新たな可能性として水素吸入療法への関心が高まっています。ここでは、特に信頼性の高いランダム化比較試験(RCT)と大規模観察研究の結果から、水素吸入療法が糖尿病患者にもたらす具体的な効果について解説します。
水素吸入を併用し血糖値コントロールが改善

2022年に中国で行われた臨床試験では、メトホルミン(代表的な糖尿病の薬)だけでは血糖コントロールが不十分だった2型糖尿病患者110人を対象に、「メトホルミン+水素吸入」と「メトホルミン+空気の吸入(プラセボ)」に分けて、効果を比較しました。4)
12週間後の結果として、水素吸入を併用した場合に大きな改善を示し、具体的に以下の変化が見られました。
| 水素吸入を併用 | 標準治療のみ | |
| HbA1c(%) | 9.04 → 8.26 (8.6%低下)* | 8.99 → 8.93 (0.67%低下) |
| 空腹時血糖 (mmol/L) | 9.56 → 8.66 (9.4%低下)* | 9.47 → 9.98 (5.4%増加)* |
| 食後2時間血糖 (mmol/L) | 17.30 → 15.40 (11%低下)* | 16.77 → 17.47 (4.2%増加)* |
HbA1c(ヘモグロビン・エーワンシー)は、過去1~2ヶ月の血糖状態を反映する重要な指標です。一般に合併症予防のために7.0%未満を目指します。「HbA1cが1%低下すると合併症リスクが約20%減少する」との報告5)もあるため、水素吸入による0.8%の改善は非常に意味のある変化です。
また標準治療だけを受けたグループでは空腹時や食後の血糖値が悪化したのに対し、水素吸入を併用したグループではしっかり改善しました。これは日常生活の中で血糖値の乱高下が少なくなり、高血糖による体のダメージが減ることを意味します。
2023年に1,088人を対象にした別の大規模研究でも、水素吸入併用はHbA1cを0.94%低下させ、標準治療だけの0.46%低下と比べて約2倍の効果を示しました。6)
これらの結果から、既存の糖尿病治療に水素吸入療法を併用することで、血糖値のコントロールをより効果的に改善する可能性があると考えられます。
水素吸入を併用しコレステロール値が改善

水素吸入療法は血糖値だけでなく、血中のコレステロール値にも良い影響を与えることがわかっています。
上述の、同じ臨床試験による各コレステロール値の変化は以下の通りです。4)
| 指標(mmol/L) | 水素吸入を併用 | 標準治療のみ |
| 中性脂肪(トリグリセリド) | 2.18→1.99 (約9%改善)* | 2.17 → 2.16 (ほぼ変化なし) |
| 総コレステロール | 6.13 → 5.52 (約10%改善)* | 5.93 → 6.35 (約7%悪化)* |
| 善玉コレステロール(HDL) | 1.18 → 1.22 (約3%増加)* | 1.20 → 1.25 (約4%増加)* |
| 悪玉コレステロール(LDL) | 3.92 → 3.45 (約12%改善)* | 3.99 → 3.91 (約2%改善)* |
特に注目すべきは総コレステロールと悪玉コレステロール(LDL)の改善です。水素吸入を併用したグループでは、総コレステロールが約10%、LDLが約12%も低下しており、これは一部のコレステロール低下薬に近い効果です。
対照的に、標準治療だけのグループでは総コレステロールが増加しており、血糖と脂質の両方をコントロールすることの難しさがうかがえます。
また別の日本の研究では、水素水を飲むことでLDLの「質」が改善することも確認されています。小さくて酸化した悪玉コレステロール(特に動脈硬化を引き起こしやすい種類)が減ることで、心臓病や脳卒中のリスク低減につながる可能性があります。7)
これらの結果は、糖尿病の治療に水素吸入を併用することで、血糖だけでなくコレステロール値も同時に改善し、動脈硬化や心筋梗塞、脳卒中などの合併症リスクを総合的に低下させる可能性を示しています。
水素吸入を併用しインスリンの効きが改善

血糖値とコレステロール値に加え、2型糖尿病の根本的な問題である「インスリンの効きにくさ(インスリン抵抗性)」と「膵臓からのインスリン分泌能力(β細胞機能)」も水素吸入によって改善する可能性があります。
同じ臨床試験での測定結果は以下の通りです。4)
| 水素吸入を併用 | 標準治療のみ | |
| インスリン抵抗性 (HOMA-IR) | 3.71→3.63 (2%改善)* | 3.61 → 3.86 (悪化)* |
| 膵臓のインスリン分泌能力 (HOMA-β) | 31.02 → 32.39 (約4.4%改善)* | 30.01 → 30.60 (約2%改善) |
HOMA-IRは値が低いほどインスリンが効きやすい状態を、HOMA-βは値が高いほど膵臓の機能が保たれていることを示します。水素吸入を併用したグループではインスリンの効きが良くなり、同時に膵臓の機能も改善しているのに対し、標準治療だけのグループではインスリン抵抗性が悪化しています。
別の研究でも同様に、水素吸入を併用したグループではそうでない場合に比べてインスリン抵抗性の改善が約4.5倍、β細胞機能の向上が約4倍という結果が出ています。6)
これらの結果は、水素吸入が糖尿病の二大問題「インスリンが効きにくい」「インスリンが足りない」の両方を改善する可能性を示しており、特に長期的な病気の進行を遅らせる効果が期待できます。
水素吸入を併用し治療の副作用が軽減

これだけ効果があるなら「副作用はないの?」と心配になるかもしれません。一般に薬の効果と副作用はトレードオフの関係にあることが多いです。
しかし水素吸入療法の特長の一つが、副作用が極めて少ないことです。むしろ、既存の糖尿病薬による副作用を減らす効果さえあります。
2型糖尿病患者1,088人を対象にした研究では、水素吸入を併用した場合とそうでない場合を比較して、以下のような治療の副作用発生率の違いが報告されています。6)
| 副作用 | 水素吸入を併用 | 標準治療のみ |
| 低血糖 | 2.0% | 6.8% |
| 嘔吐 | 2.6% | 7.4% |
| 便秘 | 1.7% | 4.4% |
| めまい | 3.3% | 6.3% |
特に低血糖は患者さんの生活の質(QOL)を大きく下げる症状ですが、水素吸入によってその発生率が約1/3に減少したことは大きなメリットです。
また、別の臨床試験では、なんらかの副作用が出た割合が水素吸入グループでは3.6%(55人中2人)だったのに対し、標準治療だけのグループでは32.7%(55人中18人)という驚きの結果が出ています。4)これは「100人中30人以上に副作用が出ていた治療」が「100人に4人程度まで減った」ということで、患者さんの治療継続のしやすさにも大きく貢献するでしょう。
2型糖尿病に水素吸入を取り入れる方法と注意点
これまでの研究結果を見て、「水素吸入を試してみたい」と考えた方もいらっしゃるかもしれません。
そういった方に向けて、ここでは水素吸入を取り入れる方法とその際の注意点についてお伝えします。
水素吸入を取り入れる方法
水素吸入は、主に以下の場所や方法で利用できます。それぞれ特徴が異なるため、ご自身の状況に合わせて検討しましょう。
①医療機関(自由診療)
一部のクリニックなどでは、医師の管理下で水素吸入療法を自由診療として提供しています。
病状を把握している医師のもとで受けられる安心感がありますが、提供している医療機関はまだ限られています。
②水素吸引サロン
健康増進やリラクゼーション目的で、水素吸入サービスを提供するサロンや専門店も増えています。
手軽に試せる一方、医療機関ではないため、ご自身の健康状態については自己責任で判断する必要があります。
家庭用吸入器
自宅で好きな時に吸入できる家庭用の水素吸入器も市販されています。初期費用はかかりますが、長期的に見るとコストを抑えられる可能性があります。
ただし、機器の種類によって水素の発生方式や濃度、安全性などが大きく異なるため、機器選びは慎重に行う必要があります。
水素吸入サロンでの水素吸入や家庭用の水素吸入器を導入する前に知っておきたいことは、以下の記事でまとめています。ぜひ、ご参考ください。
>> 水素吸入サロンの「料金相場」は1時間3000円!プランと選び方を解説
>> 水素吸入器を「購入・レンタルする前」に知っておきたいことまとめ
水素吸入を始める際の注意点
水素吸入を検討する際には、以下の点を必ず守ってください。
注意点①:標準治療は絶対に継続する
最も重要な注意点です。水素吸入は、あくまで2型糖尿病の標準治療(食事療法、運動療法、医師から処方された薬物療法)を補助する可能性のあるものです。水素吸入を始めたからといって、決して自己判断で薬を減らしたり、治療を中断したりしないでください。血糖コントロールが悪化し、深刻な事態を招く可能性があります。
注意点②:効果の過信は禁物、個人差を理解する
紹介した研究結果は有望ですが、まだ研究段階であり、すべての人に同じ効果が現れるとは限りません。効果の感じ方には個人差があることを理解し、「これだけで治る」といった過度な期待はしないでください。
注意点③:必ずかかりつけ医に相談する
水素吸入を始める前には、必ずあなたの糖尿病の状態をよく知るかかりつけ医に相談してください。特に、他の病気(心臓病、腎臓病など)がある方や、複数の薬を服用中の方は、相互作用などの予期せぬ影響がないかを確認する必要があります。継続中も定期的に医師の診察を受け、体の状態をチェックしてもらいましょう。
注意点④:信頼できる情報・機器を選ぶ
インターネット上には、水素吸入の効果を過大に宣伝する情報や、信頼性の低い機器も存在します。「必ず治る」「奇跡の治療法」といった言葉には注意し、科学的根拠に基づいた冷静な判断を心がけましょう。家庭用機器を選ぶ際も、安全性や性能に関する客観的な情報を確認することが大切です。選び方については以下の記事もご参考ください。
>> 失敗しない水素吸入器の選び方|9つのポイント解説
注意点⑤:費用について理解しておく
現在、水素吸入療法は公的医療保険の適用外であり、すべて自由診療(全額自己負担)となります。医療機関やサロンの場合は1時間3,000円ほどが相場です。家庭用機器は数十〜数百万円ほどで、維持にも費用がかかります。継続的に利用する場合のコストも考慮し、無理のない範囲で検討しましょう。
以上5つの注意点を十分に理解し、かかりつけ医とよく相談した上で、ご自身にとって水素吸入が適切な選択肢かどうかを慎重に判断するようにしてください。
まとめ:2型糖尿病の補助治療としての水素吸入の可能性
2型糖尿病に対する水素吸入療法は、既存の治療法を補完する新たな選択肢として期待されています。これまでの研究結果から、血糖値や脂質異常の改善に加えてインスリンの働きを回復させる可能性が示されています。また、副作用がなく、既存の治療薬の副作用軽減にもつながる可能性があり、そういった側面でも標準治療の補助として期待が寄せられています。
ただし、現時点では「有望だが研究途上」の段階です。研究数がまだ限られており、長期間の効果や合併症予防の証拠が十分ではありません。また、なぜ・どのように効果があるのかという詳細なメカニズムについても研究が進行中です。
水素吸入療法は決して従来の食事・運動療法や薬物療法の「代わり」ではなく、それらを「サポートする選択肢」として考えるべきでしょう。ただ、既存治療だけでは十分な効果が得られない方や、薬の副作用に悩む方にとっては、検討する価値のある新たな治療法かもしれません。
今後さらに研究が進み、この治療法の位置づけがより明確になることが期待されています。
参考文献
- 国民健康・栄養調査(令和5年)|厚生労働省
- 国民健康・栄養調査(令和元年)|厚生労働省
- Ohsawa, I., Ishikawa, M., Takahashi, K., Watanabe, M., Nishimaki, K., Yamagata, K., Katsura, K., Katayama, Y., Asoh, S., & Ohta, S. (2007). Hydrogen acts as a therapeutic antioxidant by selectively reducing cytotoxic oxygen radicals. Nature medicine, 13(6), 688–694. https://doi.org/10.1038/nm1577
- Lin, G., & Ni, T. (2022). Efficacy and safety of hydrogen inhalation therapy in type 2 diabetes mellitus patients inadequately controlled by metformin alone. Advances in Clinical Medicine, 12(10), 9605–9612. https://doi.org/10.12677/acm.2022.12101389
- 糖尿病|厚生労働省
- Zhao, Z., Ji, H., Zhao, Y., Liu, Z., Sun, R., Li, Y., & Ni, T. (2023). Effectiveness and safety of hydrogen inhalation as an adjunct treatment in Chinese type 2 diabetes patients: A retrospective, observational, double-arm, real-life clinical study. Frontiers in endocrinology, 13, 1114221. https://doi.org/10.3389/fendo.2022.1114221
- Kajiyama, S., Hasegawa, G., Asano, M., Hosoda, H., Fukui, M., Nakamura, N., Kitawaki, J., Imai, S., Nakano, K., Ohta, M., Adachi, T., Obayashi, H., & Yoshikawa, T. (2008). Supplementation of hydrogen-rich water improves lipid and glucose metabolism in patients with type 2 diabetes or impaired glucose tolerance. Nutrition research (New York, N.Y.), 28(3), 137–143. https://doi.org/10.1016/j.nutres.2008.01.008
このコラム記事は、一般的な医学的情報および最新の研究動向をもとに作成しておりますが、読者の方の個別の症状や体質などを考慮したものではありません。また、医学的アドバイス、診断、治療に代わるものではなく、特定の製品や治療法の効果・効能を保証、証明するものでもありません。健康上の問題がある場合は、自己判断せずに医療機関を受診し、医師などの専門家に必ずご相談ください。本コラム記事の情報をもとに被ったいかなる損害についても、当方は一切の責任を負いかねます。
※本記事は、公開時点での情報に基づいて作成しており、最新のものと異なる場合があります。予めご了承ください。

本記事は医療健康情報を含むコンテンツを専門医が確認する「メディコレWEB」の認証を受けています。
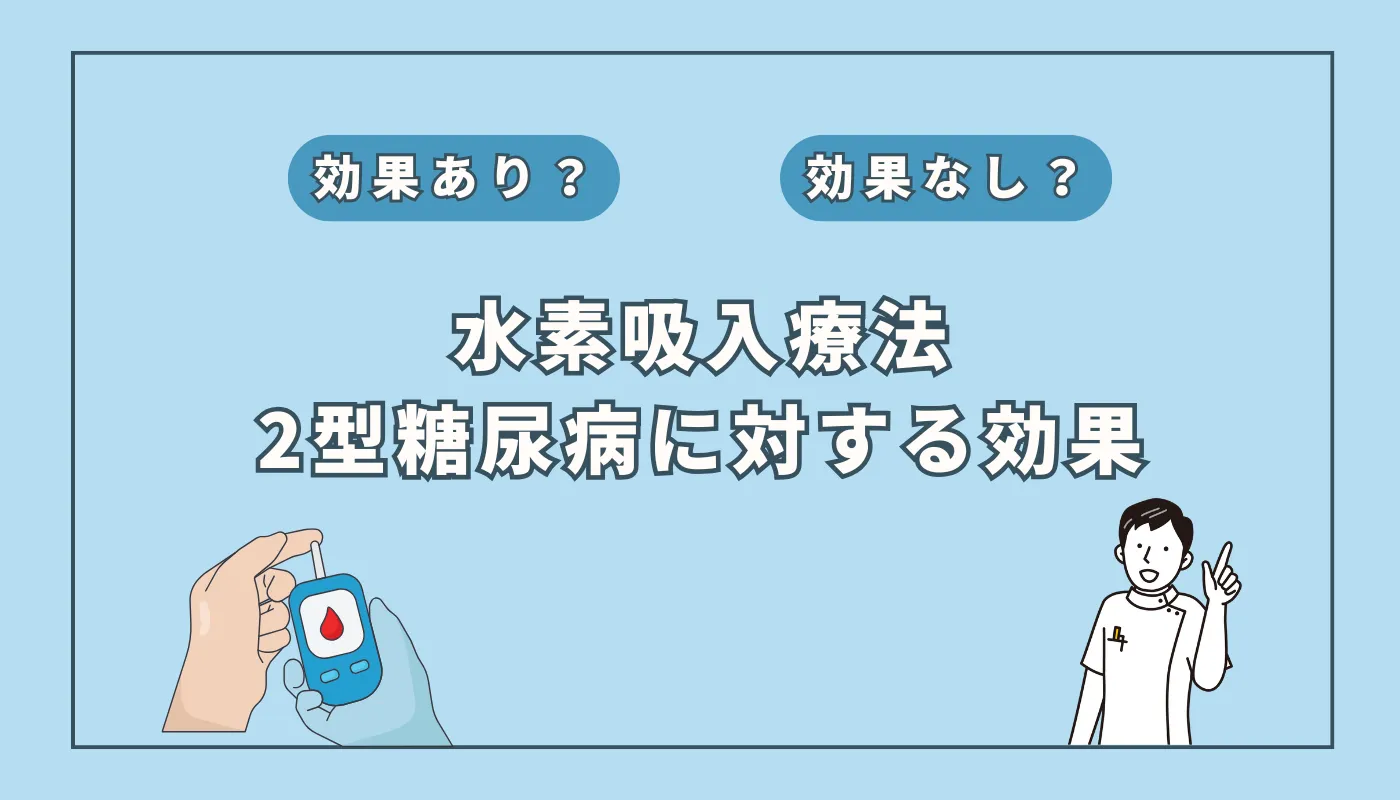
医師
中路幸之助 先生
これまでの研究において、水素吸入による血糖・脂質改善が見られたのは非常に興味深いデータと言えます。また、既存治療の副作用軽減や治療効果の向上に寄与する可能性が示されている点は患者さんにとって朗報かもしれません。標準治療が大前提ですが、補助療法として検討する場合は、担当医師にご相談の上判断するようにしてください。