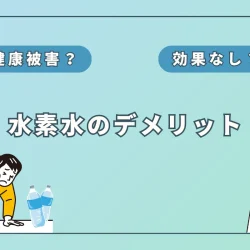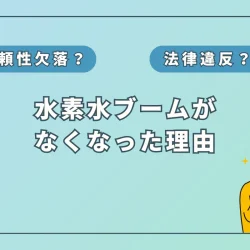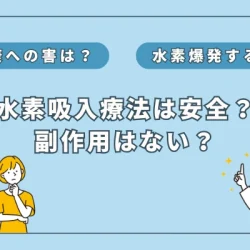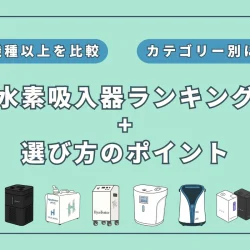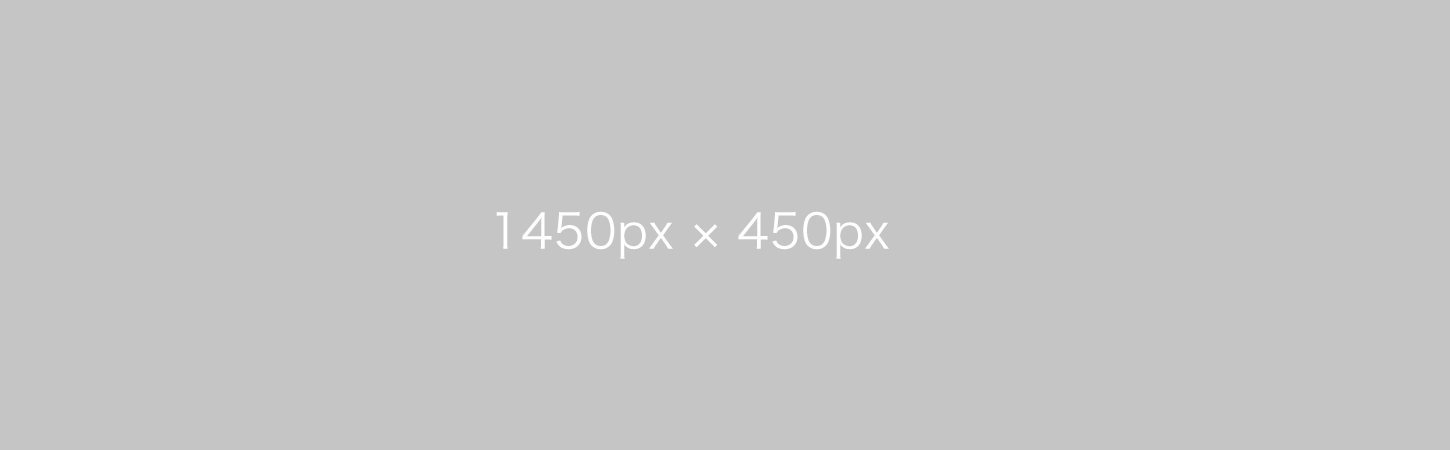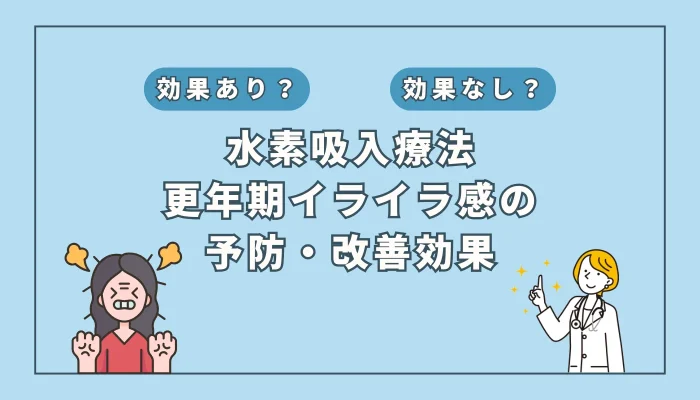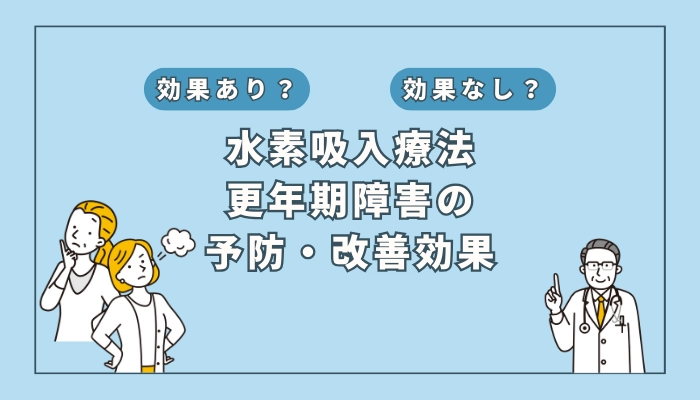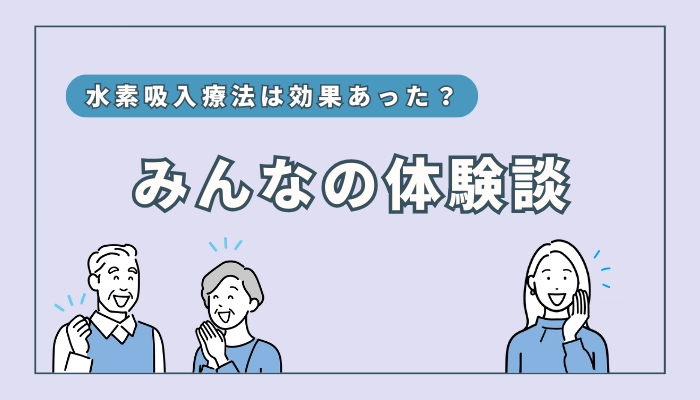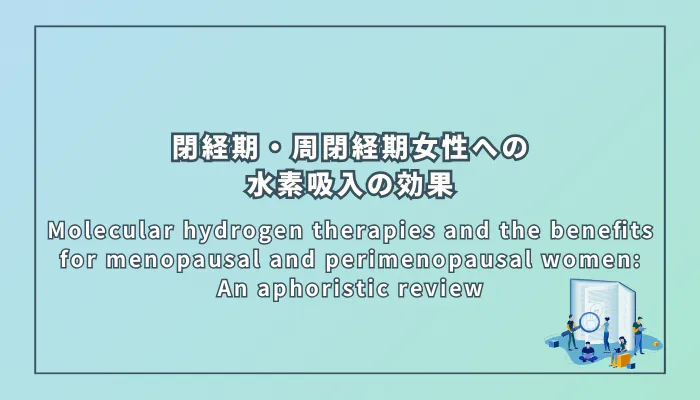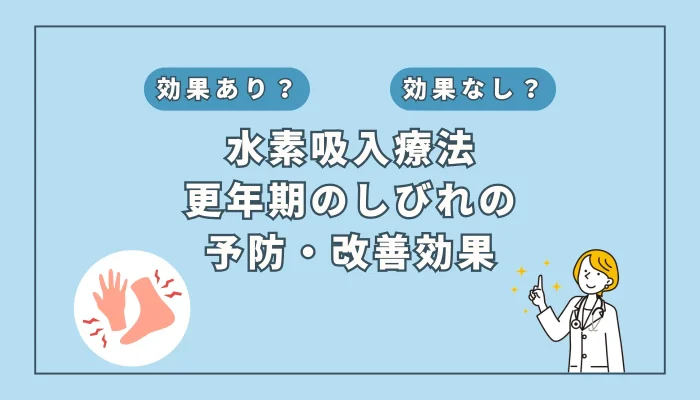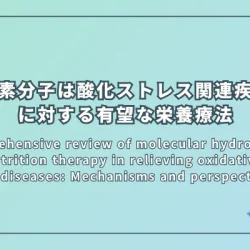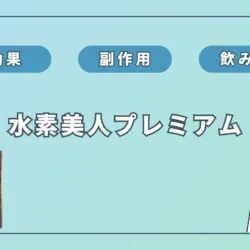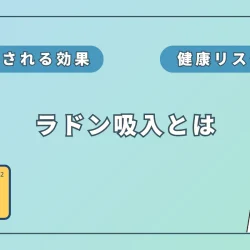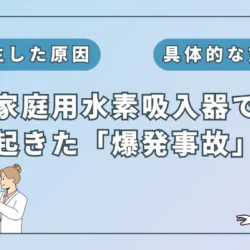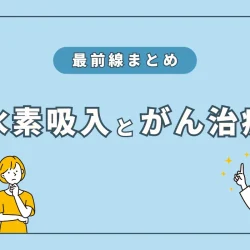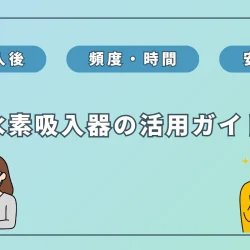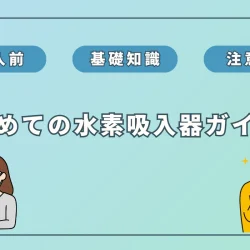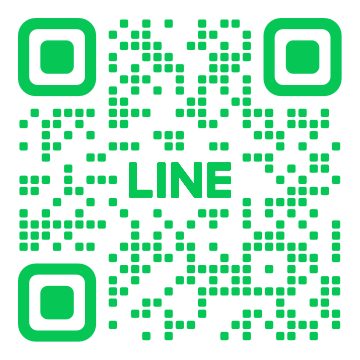《この記事の執筆者》

2011年国立大学医学部卒。初期臨床研修を経て総合診療医として勤務しながら、さまざまな疾患の患者さんに向き合う治療に従事。医療行政に従事していた期間もあり、精神福祉、母子保健、感染症、がん対策、生活習慣病対策などに携わる。結核研究所や国立医療科学院での研修も積む。2020年からは医療法人ウェルパートナーで主任医師を勤める。
「最近、普段気にならないことに敏感になって、イライラする…」
もしかしたら、それは更年期によるイライラかもしれません。
更年期での女性ホルモンの減少による心身の不調は、時に家庭や職場での人間関係にも影響を与え、孤独感やストレスを招くこともあり注意が必要です。
本記事では、更年期のイライラの原因や治療法などから、最新研究や専門家の意見をもとに、水素吸入がもたらす可能性を詳しく解説します。更年期障害のイライラにお悩みの方はぜひご参考ください。
現時点では、水素吸入が更年期障害のイライラ感に直接的な効果をもたらすことを裏付けるヒト臨床試験は存在しない。ただし、酸化ストレスがイライラ感の一因とされる研究があり、水素吸入の可能性が理論的に期待される段階。
(すいかつねっとのエビデンス評価基準はこちら)
更年期障害のイライラ感について

更年期とは、閉経前後10年間の時期を指します。
更年期は女性のライフステージの一つですが、女性ホルモン(エストロゲン)の分泌量が急激に変化するため、心身にさまざまな不調を引き起こします。
特にイライラ感や攻撃性の高まりなどの精神的な不調に悩まされる女性は多く、社会生活や家庭生活に大きな影響を与えるケースも少なくありません。
気持ちが落ち着かないことで外出ができなくなる、社会との交流を避けるようになる、など活動性の低下を引き起こす場合もあります。
更年期障害のイライラ感は深刻な症状の一つです。まずは、イライラ感の原因、症状、治療方法について詳しく見てみましょう。
更年期障害のイライラ感の原因
更年期障害で生じるイライラ感の根本的な原因は、女性ホルモンの一種であるエストロゲンの分泌低下です。
エストロゲンは女性の心身バランスを整えるホルモンでもあります。不足すると気分を落ち着かせるセロトニンなどの分泌量も減るため、イライラ感が高まりやすいと考えられています。
また、エストロゲンの減少による自律神経バランスの乱れもイライラ感の原因として挙げられます。
さらに、更年期障害はホットフラッシュ、便秘、しびれ、睡眠不足などさまざまな不調を引き起こします。これらの不調がイライラ感につながるケースも少なくありません。
更年期障害のイライラ感の症状
更年期障害では気分が落ち着かず、些細なことでイライラしやすくなる症状が現れやすいとされています。
更年期障害によるイライラ感には次のような特徴があります。
- 普段気にならないことに敏感になる
- 感情の制御が突然できなくなり、周囲に当たってしまう
- 集中力や判断力が低下する
- 周囲との関係が悪化することで孤独を感じやすくなる
- 良眠が妨げられ、肩こりや頭痛などの症状を伴うことがある
このような精神的な不調は周囲から理解されにくいのも、さらなる不調の原因となります。
更年期障害による気分の変調は自分の意思で抑えられないことも多いため、症状に悩んだときは軽く考えずに周囲に相談したり、適切な治療や対策を行うことが大切です。
更年期障害のイライラ感の対策・治療方法
更年期障害によるイライラ感に悩まされたときには、以下のような生活習慣の見直しが必要です。
- 適度な運動や趣味などで気分をリフレッシュする
- 十分な休息や睡眠時間を確保する
- バランスのとれた食生活を心がける
一方で、このような生活改善をしてもイライラ感が続く場合には気持ちを落ち着かせるための薬物療法、不足したエストロゲンを補うためのホルモン補充療法などを行う必要があります。
また、精神的な苦痛が強い場合にはカウンセリングなども効果的です。
イライラ感に悩んだときは、ご自身に合った解決方法を見つけましょう。
水素吸入が更年期障害のイライラ感の予防や改善に役立つ可能性

更年期障害のイライラ感は単なる気分の変調に留まらず、長引く場合には日常生活にも支障を来す症状の一つです
適切な対策や治療が必要ですが、実際にご自身に合った解決方法を見つけられる女性は少ないかもしれません。
これまでにも更年期障害のイライラ感を予防、改善する方法を見出す研究はさまざま行われてきました。
現在のところ水素吸入がイライラ感の予防や改善に効果を示すという研究結果は報告されていません。
一方で、水素吸入で除去できる活性酸素がイライラ感を引き起こす可能性を示す研究結果は報告されています。具体的な内容を詳しく見てみましょう。
酸化ストレスによる神経の炎症が攻撃性を高める?
2023年、ポルトガルの研究チームは酸化ストレスによる神経の慢性的な炎症が攻撃性を高める可能性を示唆する総説論文を報告しました1)。
総説論文はこれまで行われてきたさまざまな研究結果をまとめて新たな結論を導き出す論文のことです。
この総説論文では、酸化ストレスによる神経炎症が攻撃性の増加につながる可能性を指摘しています。
また、酸化ストレスがストレスを引き起こすホルモン分泌を増加させることで攻撃性を高める可能性も示唆しました。
水素吸入が更年期障害のイライラ感を予防する可能性
これまでの研究結果から、更年期の女性は活性酸素が増えて酸化ストレスが高まることが明らかになっています2)。酸化ストレスが心身の不調の原因になるとも考えらえているのです。
今回の総説論文の説が正しいとすれば、更年期障害の攻撃性を伴うイライラ感も酸化ストレスが関係している可能性があると言えるでしょう。そのため、酸化ストレスを効率よく軽減できる水素吸入は更年期障害のイライラ感を予防できる可能性があると考えられます。
実際の効果を立証するにはさらなる研究が必要ですが、この総説論文の結果は水素療法の新たな可能性を示す光になったと考えます。
抗酸化物質がイライラ感を改善する?
2021年、中国の研究チームは強力な抗酸化作用を持つN-アセチルシステインの投与が過敏性を伴うイライラ感を改善する可能性を示す研究結果を明らかにしました3)。
この研究は自閉症スペクトラム障害を持つ小児を対象に行われ、N-アセチルシステインを投与した群と投与していない群に分けて症状の変化を検証しています。その結果、N-アセチルシステインを投与した群は有意にイライラ感が改善したことが明らかになりました。
研究者たちは、自閉症スペクトラム障害では活性酸素の増加が認められ、酸化ストレスが症状の重症度にも関係している可能性を指摘しています。
水素吸入が更年期障害のイライラ感を改善する
今回の研究は自閉症スペクトラム障害の小児を対象とした研究ですが、更年期障害と同じく体内の酸化ストレスがさまざまな症状を引き起こす可能性が指摘されています。
そのため今回の研究結果を考察すれば、更年期障害でも抗酸化物質がイライラ感を改善させる可能性はあると考えられるでしょう。
抗酸化作用がある水素吸入でイライラ感が改善する可能性もあると考えられます。
【私はこう考える】水素吸入と更年期のイライラ感
更年期障害によるイライラ感は心身の負担になりやすい症状であり、さらには日常生活にも大きな支障を及ぼす可能性があります。イライラ感が続くときは適切な対策や治療が必要です。
今回ご紹介した2つの研究結果は、更年期障害によるイライラ感の予防や改善に水素吸入が役立つ可能性を示唆していると考えます。
いずれも更年期障害の患者を対象とした研究結果ではありませんが、酸化ストレスがイライラ感を高める可能性があるとするメカニズムは共通しています。そのため、抗酸化物質が更年期障害のイライラ感を改善する可能性もあると言えるでしょう。
まだ理論的な考察の域に留まりますが、この2つの研究結果は実際の人を対象とした貴重な研究です。このような研究結果を参考に水素吸入の可能性を考察し、多くの症状や病気の予防、治療に応用される道を探していきたいと思います。
更年期障害のイライラ感の予防や改善に水素吸入が応用される日はまだ遠いかもしれませんが、水素吸入は自宅でも気軽に行うことができます。
医療機関での治療に抵抗がある方も取り入れやすい対策法であるため、更年期障害のつらい症状に悩む女性のサポート役として広く認識される日が来ることを期待します。
参考文献
- Correia, A. S., Cardoso, A., & Vale, N. (2023). Oxidative Stress in Depression: The Link with the Stress Response, Neuroinflammation, Serotonin, Neurogenesis and Synaptic Plasticity. Antioxidants, 12(2), 470. https://doi.org/10.3390/antiox12020470
- Doshi, S. B., & Agarwal, A. (2013). The role of oxidative stress in menopause. Journal of mid-life health, 4(3), 140–146. https://doi.org/10.4103/0976-7800.118990
- Chen, L., Shi, X. J., Liu, H., Mao, X., Gui, L. N., Wang, H., & Cheng, Y. (2021). Oxidative stress marker aberrations in children with autism spectrum disorder: a systematic review and meta-analysis of 87 studies (N = 9109). Translational psychiatry, 11(1), 15. https://doi.org/10.1038/s41398-020-01135-3
このコラム記事は、一般的な医学的情報および最新の研究動向をもとに作成しておりますが、読者の方の個別の症状や体質などを考慮したものではありません。また、医学的アドバイス、診断、治療に代わるものではなく、特定の製品や治療法の効果・効能を保証、証明するものでもありません。健康上の問題がある場合は、自己判断せずに医療機関を受診し、医師などの専門家に必ずご相談ください。本コラム記事の情報をもとに被ったいかなる損害についても、当方は一切の責任を負いかねます。