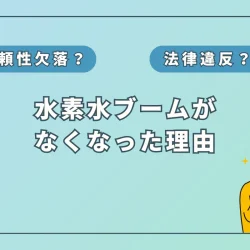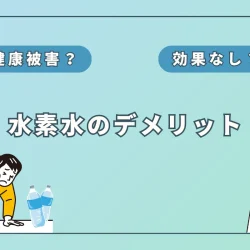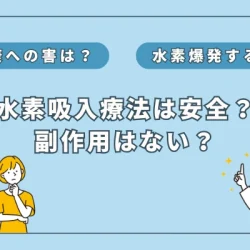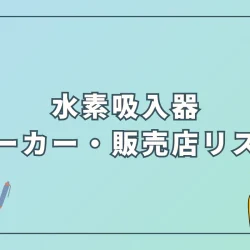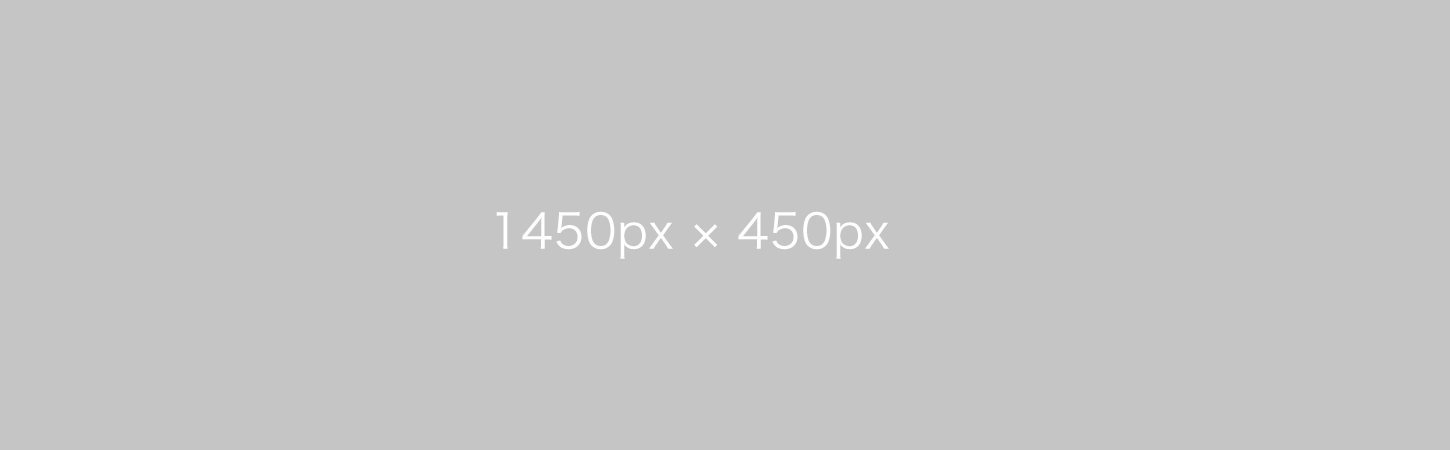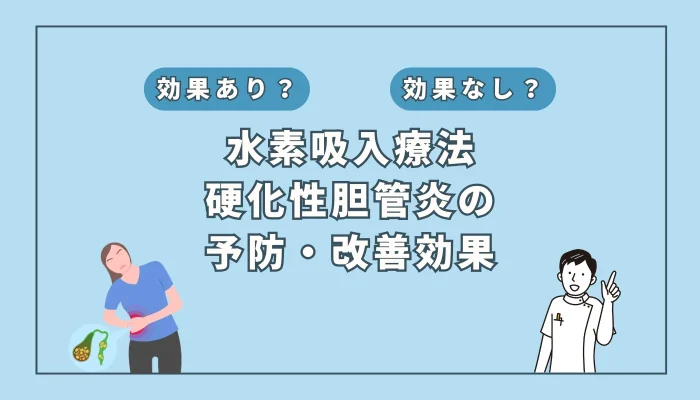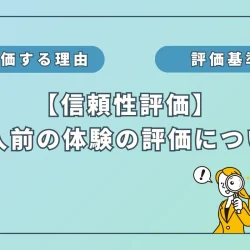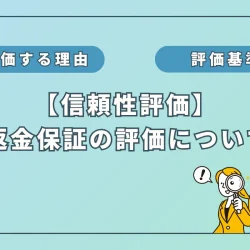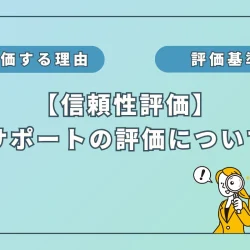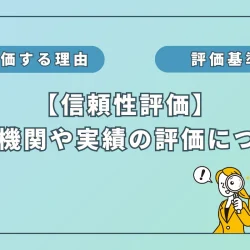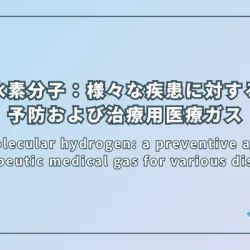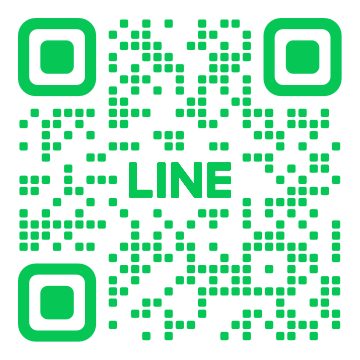《この記事の監修者》

国立大学医学部卒。卒後は消化器内科医として様々な市中病院で研鑽を積み、現在に至る。専門は早期がんの内視鏡治療、炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病)の診療、消化器がんの化学療法。消化器病学会専門医,消化器内視鏡学会専門医,総合内科専門医を取得。
肝臓の沈黙の悲鳴、硬化性胆管炎。
原因不明の難病とされ、有効な治療法が確立されていないこの病気に、今、新たな希望の光が見え始めています。
それが、水素吸入療法です。
本記事では、硬化性胆管炎の症状、原因、従来の治療法に加え、最新研究で示唆される水素吸入の驚くべき可能性を解説します。
水素吸入が硬化性胆管炎の予防や進行抑制に寄与する可能性は、水素水と動物実験により示唆されている。ただし、ヒトを対象とした臨床研究はなく、有効性を判断するにはさらなる検証が必要な段階。
(すいかつねっとのエビデンス評価基準はこちら)
硬化性胆管炎とは?
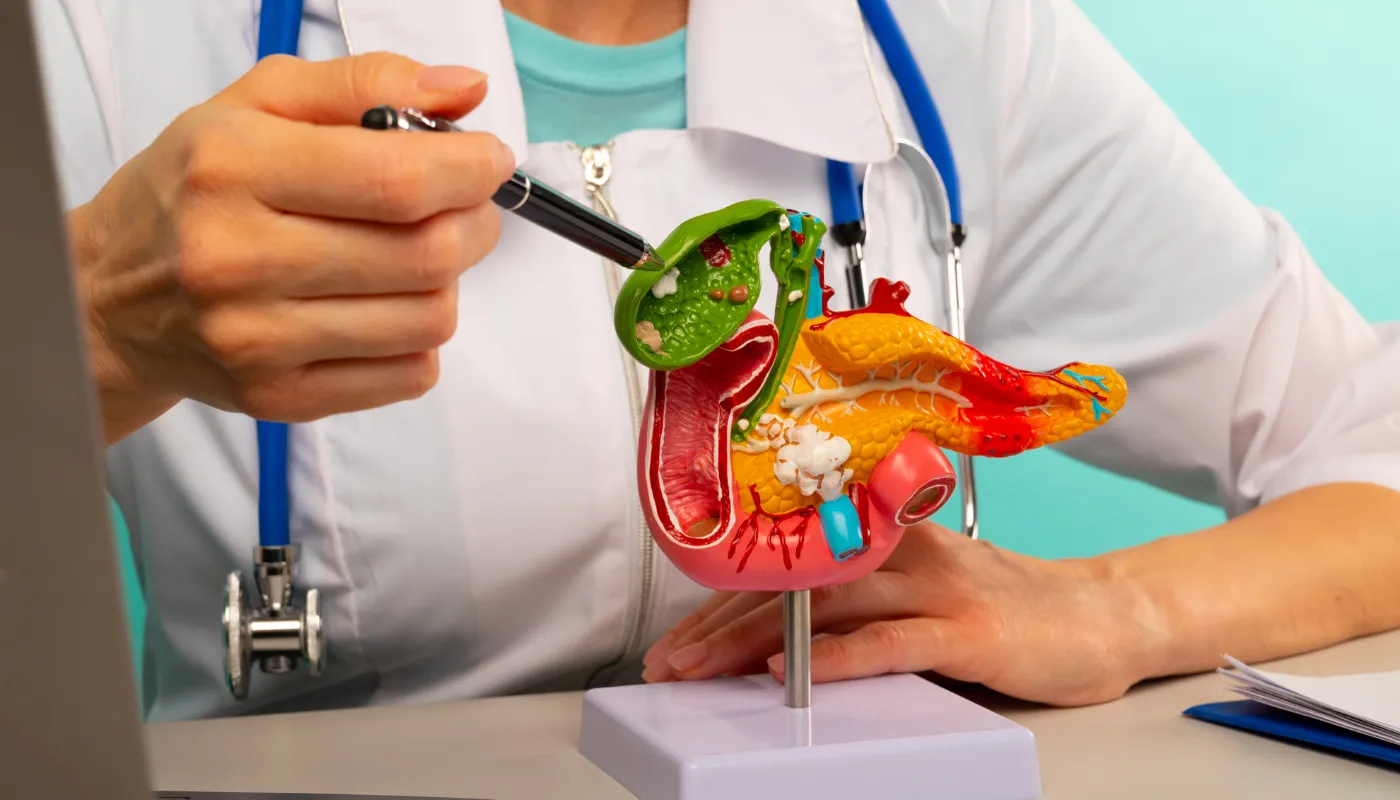
硬化性胆管炎は、肝臓の内外にある胆管が炎症を起こし、硬くなることで、胆汁の流れが悪くなる進行性の病気です。
胆汁は、脂肪の消化を助けるなど、体にとって重要な役割を担っています。胆汁がうまく流れなくなると、「胆汁うっ滞」という状態になり、肝臓にダメージを与え、最終的には肝硬変や肝不全を引き起こす可能性があります。
硬化性胆管炎の中でも原因不明の「原発性硬化性胆管炎(PSC)」は、日本では推定2,300人が発症しているとされる稀な疾患で、厚生労働省の指定難病に指定されています。1)
患者数は2007年から2018年の10年間にかけて2倍になり、世界的にみても増加傾向にあります。
硬化性胆管炎の種類および原因
硬化性胆管炎にはいくつかの種類があり、それぞれ異なる特徴と原因を持っています。
原発性硬化性胆管炎(PSC)は、原因が特定されていない慢性進行性の疾患で、肝臓の内外の胆管に炎症や線維化、狭窄が生じます。この病気は日本では原発性硬化性胆管炎患者さん全体の約40%、若い患者さんでは約60%に炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病)が合併することも知られています。1)
>> 【医師監修】潰瘍性大腸炎の新治療法?水素吸入の効果と可能性
>> 【医師監修】クローン病に水素吸入は有効?最新治療法とエビデンスを解説
IgG4関連硬化性胆管炎(IgG4-SC)は、IgG4関連疾患の一種で、胆管壁の肥厚や長い狭窄が見られる病気です。この疾患は血中IgG4値の上昇や画像所見などを基に診断されます。
二次性硬化性胆管炎(SSC)は、他の明確な原因によって引き起こされる硬化性胆管炎です。その原因としては、胆道感染症(例:AIDS関連胆管炎)、総胆管結石や肝内結石症、外傷や胆道手術後の影響、動注化学療法や腐食性物質による胆管傷害などが挙げられます。また、先天的な胆道形成異常や感染症(細菌、ウイルス、真菌など)が関与する場合もあります。
硬化性胆管炎の主な症状
硬化性胆管炎は、初期段階では自覚症状がない場合も多いです。
しかし、病気が進行するにつれて、疲れやすさ、皮膚のかゆみ、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、腹痛などが現れてきます。
また、胆管炎を繰り返すことがあり、発熱、悪寒、右上腹部の痛みなどの症状を伴うこともあります。
進行すると、肝硬変や肝不全を引き起こすことがあるため注意が必要です。
硬化性胆管炎の一般的な治療法
現在のところ、原発性硬化性胆管炎を根本的に治す治療法は確立されていません。
治療は、症状を和らげ、胆管炎を予防し、合併症を管理することが中心となります。
薬物療法としては、ウルソデオキシコール酸などの胆汁の流れを良くする薬、ベザフィブラートなど中性脂肪を下げる薬も有効とされています。。
最終的には、肝移植が必要になることもあります。
IgG4関連硬化性胆管炎はステロイド療法が非常に有効とされています。
二次性硬化性胆管炎の治療は原因に応じて行われますが、進行した場合には肝移植が必要になることもあります。
また、いずれの硬化性胆管炎の場合であっても、内視鏡を使って胆管の狭くなっている部分を広げる治療が行われることもあります。
水素吸入療法は硬化性胆管炎に効果がある?

水素吸入療法は、水素ガスを直接吸入して体内に取り込む方法です。
近年、水素には抗酸化作用や抗炎症作用があるのではないかと期待され、さまざまな疾患分野で研究が進められています。
硬化性胆管炎においても、酸化ストレスや炎症反応の関与が示唆されていることから、水素の抗酸化作用や抗炎症作用が役立つ可能性が考えられています。
ここでは、水素吸入と硬化性胆管炎の関係について、これまでに報告されている研究から考察していきます。
水素が胆管の線維化を抑制する
2021年の研究では、水素が硬化性胆管炎の発症予防につながる可能性を示す結果が報告されています。2)
この研究では、薬物を与えて胆管の線維化を誘発したマウスに、水素水を与えた場合(水素群)と通常の水を与えた場合(対象群)の比較検討がされました。
結果として、6ヶ月後に対象群の100%で胆管の線維化が発生していた一方で、水素群では12.5%(1/8匹)の発症にとどまったことが示されています。
まだ動物実験であり、水素吸入ではなく水素水が用いられていることなどから、水素吸入の有効性を示すには更なる研究は必要です。しかし、水素が硬化性胆管炎の発症予防につながる可能性が示されたことは大きな一歩と言えるでしょう。
水素が硬化性胆管炎の進行を抑制する
上述した同研究において、水素が硬化性胆管炎の進行抑制に役立つ可能性も示唆されています。2)
硬化性胆管炎は進行することで肝臓へダメージを与え、最終的に肝硬変や肝不全などの重篤な合併症につながることがあります。
今回の研究では、水素水を与えれた場合に肝臓の状態の悪化が抑えられることが示されました。
具体的には、対象群(通常水を投与)では肝臓の状態が12週目から悪化し、16週目および20週目には著しく進行していた一方で、水素群では、肝臓形態の悪化は16週目に始まり、20週目では全体のうち28.6%(2/7匹)のみでさらなる悪化が見られたとしています。
この結果から、水素が硬化性胆管炎の進行による肝臓へのダメージを抑制し、重症化を防ぐ可能性が示唆されたと言えるでしょう。
まとめ:水素吸入療法の硬化性胆管炎に対する可能性と課題
ここまで、硬化性胆管炎の概要と水素吸入療法の有効性について解説してきました。
現時点では、水素吸入療法が硬化性胆管炎に有効かどうかを直接的に調べた研究がなく、まだ有効性を裏付ける明確なエビデンスはありません。
しかし、水素水を用いた動物実験では、硬化性胆管炎の予防や進行抑制に一定の効果を持つ可能性が示唆されました。
今後、硬化性胆管炎患者さんを対象とした質の高い臨床試験を実施し、水素吸入の有効性と安全性を検証することで、硬化性胆管炎に対する有効性が確立されることを期待しましょう。
硬化性胆管炎は根本的な治療法が確立されておらず、長期にわたるケアが必要になる場合も多い疾患です。まずは標準治療に取り組み、期待したような改善が見られない場合は、主治医と相談しリスク等を考慮した上で補助的に水素吸入の活用を検討してみても良いかもしれません。
更なる検証により、水素吸入療法が硬化性胆管炎に苦しむ患者さんにとって、新たな選択肢となることを願っています。
参考文献
- 原発性硬化性胆管炎(指定難病94)|難病情報センター
- Li, C., Zhao, X., Gu, X., Chen, Y., & Yu, G. (2021). The Preventive Role of Hydrogen-Rich Water in Thioacetamide-Induced Cholangiofibrosis in Rat Assessed by Automated Histological Classification. Frontiers in pharmacology, 12, 632045. https://doi.org/10.3389/fphar.2021.632045
このコラム記事は、一般的な医学的情報および最新の研究動向をもとに作成しておりますが、読者の方の個別の症状や体質などを考慮したものではありません。また、医学的アドバイス、診断、治療に代わるものではなく、特定の製品や治療法の効果・効能を保証、証明するものでもありません。健康上の問題がある場合は、自己判断せずに医療機関を受診し、医師などの専門家に必ずご相談ください。本コラム記事の情報をもとに被ったいかなる損害についても、当方は一切の責任を負いかねます。