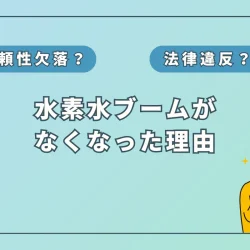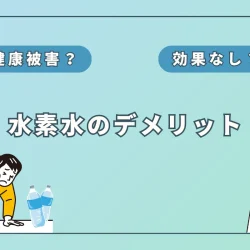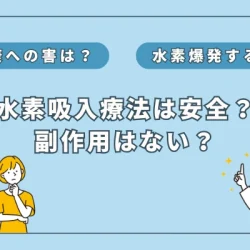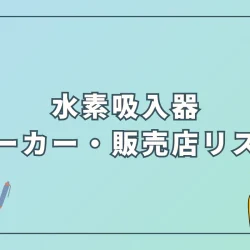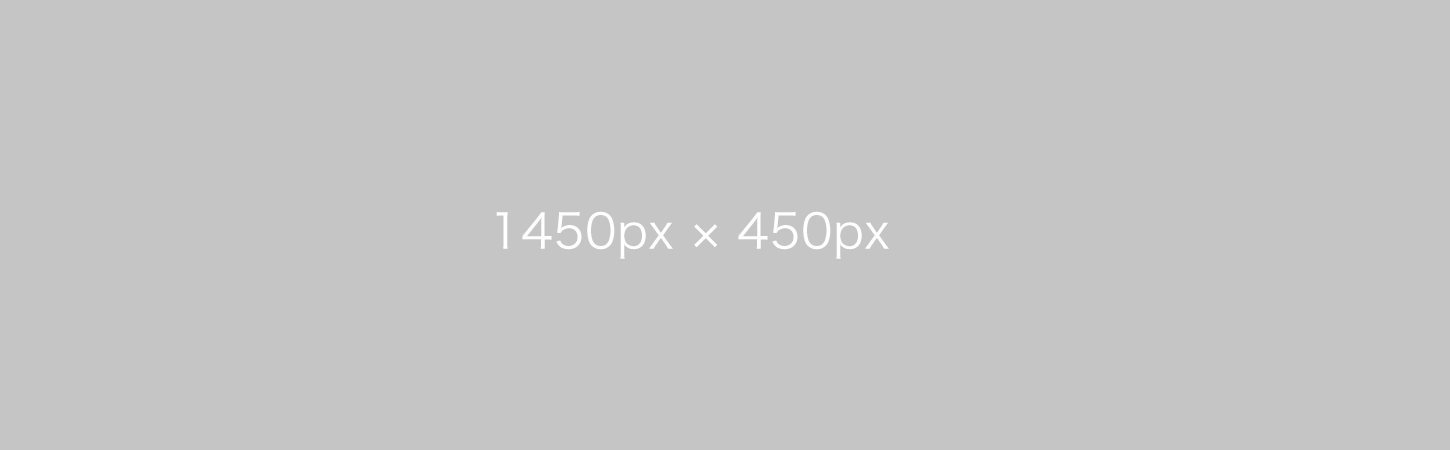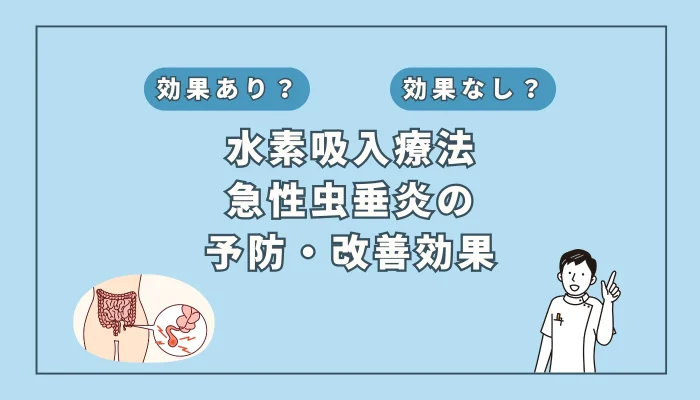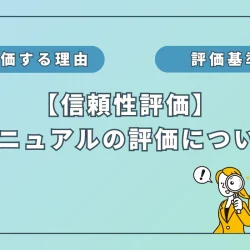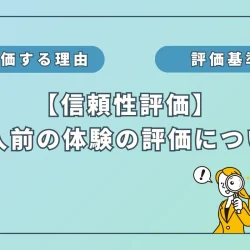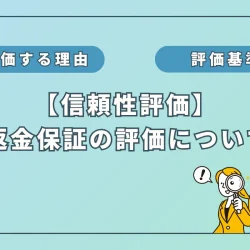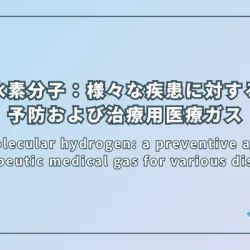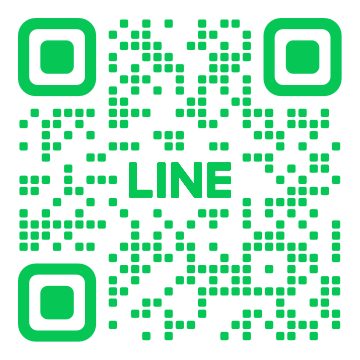《この記事の監修者》

国立大学医学部卒。卒後は消化器内科医として様々な市中病院で研鑽を積み、現在に至る。専門は早期がんの内視鏡治療、炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病)の診療、消化器がんの化学療法。消化器病学会専門医,消化器内視鏡学会専門医,総合内科専門医を取得。
「盲腸」と聞くと、手術をイメージして不安になる方もいるかもしれません。
急性虫垂炎(盲腸)は早期発見・早期治療が重要ですが、術後の回復過程も気になるポイントです。
近年、医療分野で注目を集める「水素吸入」は、そんな術後の悩みに寄り添う新たな選択肢となるかもしれません。
本記事では、急性虫垂炎の基礎知識から、水素吸入がもたらす可能性について詳しく解説します。
水素吸入が術後の炎症軽減や創傷治癒を促す可能性が示唆されているが、急性虫垂炎に特化した臨床研究は存在しない。動物実験や他疾患での報告を踏まえた推測の段階。
(すいかつねっとのエビデンス評価基準はこちら)
急性虫垂炎(盲腸)ってどんな病気?

急性虫垂炎とは、おなかの右下にある「虫垂」という小さな袋状の器官が炎症を起こす病気です。
日本語では「盲腸」と混同されることが多いですが、正確には盲腸に付属する虫垂という部位が腫れたり化膿したりする状態を指します。
急性虫垂炎は「急性腹症」と総称される腹痛症候群の中で最も多くみられ、全急性腹症の30~50%を占めるともいわれます。1)
発症年齢は10代~30代で発症が多いものの、子どもから高齢者まで幅広い年代で起こり得る病気です。
急性虫垂炎の主な原因
虫垂炎の主な原因は、虫垂の通路が何らかの理由で詰まることです。
具体的には、腸の内容物が硬くなった「糞石(ふんせき)」、リンパ組織の腫れ、まれに腫瘍などにより虫垂内が閉塞し、その結果、細菌が増殖して炎症が生じます。
炎症が進むと虫垂が腫れ上がり、組織が傷んでいく過程で強い痛みが引き起こされます。
虫垂炎の主な症状
初期にはおへその周りに鈍い痛みが生じたり、食欲不振が現れたりします。時間の経過とともに痛みの場所が右下腹部へ移動するのが典型的です。
軽い発熱や吐き気を伴うこともあります。
右下腹部を押すと強い痛みを感じたり、押した手を離したときにズキッと痛んだりするのが特徴で、検査では白血球数の上昇などが認められます。
症状が進むと虫垂が穿孔(破裂)して腹膜炎に至り、腹全体の激痛や高熱が起こることもあります。
虫垂炎の一般的な治療方法
急性虫垂炎の一般的な治療は、早期の手術(虫垂切除術)です。
特に穿孔が疑われる重症例では早めの手術が推奨されます。
最近は腹腔鏡下で手術を行うことが多いので、回復も比較的早い傾向があります。
一方、炎症が軽い場合や穿孔がない場合など、条件によっては抗生物質だけで様子をみる「保存的治療」が行われるケースもあります。
ただし、抗生物質で一時的に回復しても再発リスクがあり、最終的に手術が必要になるケースも少なくありません。
そのため現在でも手術が急性虫垂炎の標準的な治療と位置付けられています。
水素吸入療法は急性虫垂炎に効果がある?

水素吸入療法とは、水素ガスを吸入することで、体内の活性酸素を除去し、炎症を抑える効果が期待される治療法です。
水素は、体内で悪影響を及ぼす活性酸素(ヒドロキシルラジカルなど)を選択的に除去する「抗酸化作用」があることがわかっています。
この特性から、様々な疾患においてその効果検証のための研究が進められています。
しかしながら、現時点では急性虫垂炎と水素吸入の関係を直接的に調べた研究は報告されていません。
したがって、ここでは水素吸入と急性虫垂炎の関係について、既存の研究報告からその有効性の可能性について考察していきます。
有効性が期待される点1:術後の回復を促進する可能性
急性虫垂炎では、手術による虫垂切除が標準治療です。
手術後の腸管機能の回復や創部の治癒を早める方法として、炎症を抑制する水素吸入が補助的に役立つ可能性があります。
実際に2024年の脳腫瘍の術後患者を対象としたランダム化比較試験では、水素/酸素混合ガスを吸入した群で脳浮腫(むくみ)が軽減し、術後の痛みが早期に緩和されたとの報告があります。2)
これと同様に、虫垂の手術後でもガス吸入によって術後の炎症が抑えられ、痛みや回復までの期間が短縮する可能性が示唆されています。
有効性が期待される点2:傷や組織の治癒をサポートする可能性
水素には「組織修復を促進する」働きがあるとも報告されています。
例えば、放射線治療後の難治性創傷に対して長期的な水素吸入を行い、他の治療が効かなかった傷が完全治癒に至った事例が発表されています。3)
このような特性から、水素吸入は急性虫垂炎の手術創に限らず、外科処置全般の創部や炎症部分の回復を助ける補助療法として期待されています。
有効性が期待される点3:全身炎症反応の抑制
穿孔(破裂)した虫垂炎は腹膜炎を引き起こし、さらに重症化すると全身性の敗血症に発展する場合があります。
動物実験の段階ですが、水素ガスを吸入することで敗血症モデル動物の生存率が向上し、炎症マーカーの上昇が抑えられたとの報告があります。4)
このことから、虫垂炎が重症化して全身に炎症が及ぶケースでも、水素が抗酸化・抗炎症作用を通じて身体へのダメージを軽減する可能性があるかもしれません。
まとめ:水素吸入に期待される虫垂炎への応用可能性
急性虫垂炎は、比較的よく見られる病気ですが、いざ発症すると強い痛みや合併症のリスクを伴います。
現在は手術と抗生物質により、ほとんどの患者さんが回復に向かうことができます。
一方で、術後の痛みや炎症からの回復をよりスムーズにするサポート療法は、まだ十分に確立されていません。
このような状況の中、水素吸入によって術後の回復が促されたり、痛みが軽減する可能性が示されたことは、今後研究を進めていく上での大きな一歩となるでしょう。
現時点で急性虫垂炎を対象にした大規模なランダム化比較試験は行われておらず、水素吸入の有効性を示すためには科学的根拠をさらに蓄積する必要があります。
今後、水素吸入の濃度や吸入時間、手術前後のどの時期に導入すると最も効果的なのかなどを検証する研究が進めば、より具体的な治療方法が確立されるでしょう。
もし急性虫垂炎の手術を受けることになった場合、担当医に「術後回復を助けるための補助療法」に関して相談してみるのも一つの選択肢です。ただし水素吸入だけで虫垂炎を根本から治すことはできない点に留意し、あくまで標準治療を優先しながら補助療法として活用することが重要です。
参考文献
- Flum D. R. (2015). Clinical practice. Acute appendicitis–appendectomy or the “antibiotics first” strategy. The New England journal of medicine, 372(20), 1937–1943. https://doi.org/10.1056/NEJMcp1215006
- Wu, F., Liang, T., Liu, Y., Wang, C., Sun, Y., & Wang, B. (2024). Effects of perioperative hydrogen inhalation on brain edema and prognosis in patients with glioma: a single-center, randomized controlled study. Frontiers in neurology, 15, 1413904. https://doi.org/10.3389/fneur.2024.1413904
- Zhao, P. X., Luo, R. L., Dang, Z., Wang, Y. B., Zhang, X. J., Liu, Z. Y., Wen, X. H., Liu, M. Y., Zhang, M. Z., Adzavon, Y. M., & Ma, X. M. (2022). Effect of hydrogen intervention on refractory wounds after radiotherapy: A case report. World journal of clinical cases, 10(21), 7545–7552. https://doi.org/10.12998/wjcc.v10.i21.7545
- Xie, K., Yu, Y., Pei, Y., Hou, L., Chen, S., Xiong, L., & Wang, G. (2010). Protective effects of hydrogen gas on murine polymicrobial sepsis via reducing oxidative stress and HMGB1 release. Shock (Augusta, Ga.), 34(1), 90–97. https://doi.org/10.1097/SHK.0b013e3181cdc4ae
このコラム記事は、一般的な医学的情報および最新の研究動向をもとに作成しておりますが、読者の方の個別の症状や体質などを考慮したものではありません。また、医学的アドバイス、診断、治療に代わるものではなく、特定の製品や治療法の効果・効能を保証、証明するものでもありません。健康上の問題がある場合は、自己判断せずに医療機関を受診し、医師などの専門家に必ずご相談ください。本コラム記事の情報をもとに被ったいかなる損害についても、当方は一切の責任を負いかねます。