水素は、活性酸素を除去する抗酸化作用があることが知られています。
しかし、ビタミンCなどの他の抗酸化物質と何が違うのかわからない方も多いでしょう。
これらは同じ『抗酸化物質』ではあるものの、「①選択性」「②即効性」「③浸透性」「④安全性」の4つの観点で大きく異なります。
本記事では、水素とその他抗酸化物質の違いを解説し、どちらを取り入れるべきかについてもお伝えします。
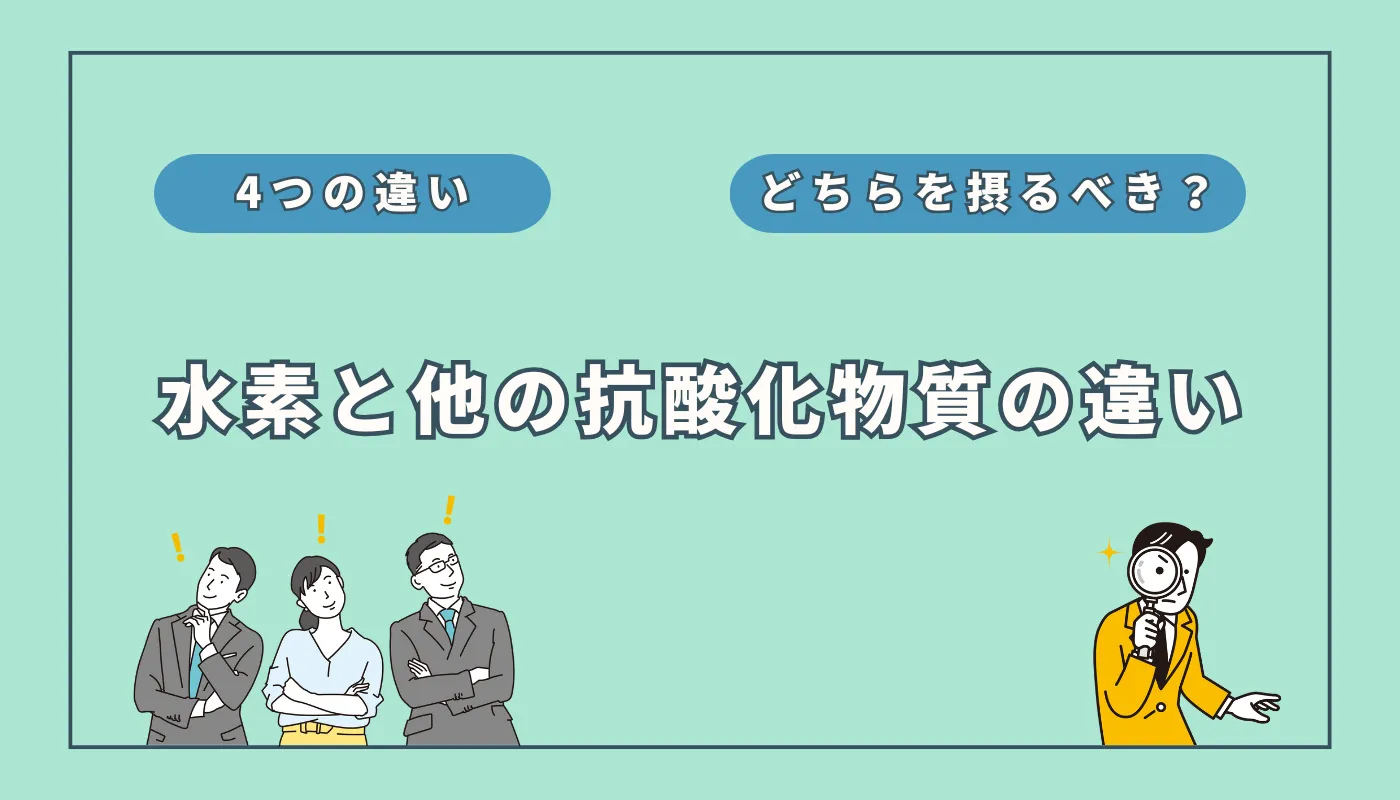
水素は、活性酸素を除去する抗酸化作用があることが知られています。
しかし、ビタミンCなどの他の抗酸化物質と何が違うのかわからない方も多いでしょう。
これらは同じ『抗酸化物質』ではあるものの、「①選択性」「②即効性」「③浸透性」「④安全性」の4つの観点で大きく異なります。
本記事では、水素とその他抗酸化物質の違いを解説し、どちらを取り入れるべきかについてもお伝えします。

抗酸化物質とは、私たちの体の中での「酸化」を防ぐ働きを持つ物質のことです。ビタミンCやポリフェノール、ビタミンEなどが代表例です。
酸化とは、切ったリンゴが茶色くなるように「サビる現象」のこと。これが老化や疲れ、さらには生活習慣病の大きな原因の一つとされています。
この酸化を引き起こす原因が「活性酸素」で、抗酸化物質はこれを除去することで、体のサビ(酸化)を防いでくれます。実際、抗酸化物質を積極的に摂ることで、老化の抑制や病気予防、美肌や健康維持につながると示唆する研究も多く存在します。
実は、「活性酸素」がすべて悪いわけではありません。
活性酸素には、体内に侵入したウイルスや細菌を攻撃して体を守る「善玉」の役割もあります。
一方で、過剰に発生し、健康な細胞まで無差別に攻撃してしまう凶悪な「悪玉活性酸素」(特にヒドロキシラジカルが有名)も存在します。私たちが対策すべきなのは、主にこの「悪玉」とされます。
ビタミンC、ビタミンE、ポリフェノール、コエンザイムQ10など、世の中には多くの抗酸化物質があります。
これらと「水素」には、以下の4つの点で違いがあります。
それぞれ具体的に見ていきましょう。
水素と他の抗酸化物質で最も重要な違いが、抗酸化作用の「選択性」です。
水素は最も有害とされる「悪玉活性酸素(ヒドロキシラジカル)」にだけ選択的に反応する性質を持っています。1)善玉活性酸素にはほとんど反応しません。
一方、ビタミンCやポリフェノールなどの抗酸化物質は、強力な抗酸化作用があるものの、必要な「善玉活性酸素」まで区別なく除去してしまいます。
水素は取り込んでから体を循環するまでのスピードが非常に速いです。
例えば、水素吸入を開始してから20分程度で血中水素濃度が安定し、全身に水素が行き渡ると報告されています。2)これは水素を消化吸収する必要がなく、その分速やかに体内に吸収されることが要因と考えられています。
一方、ビタミンCやEなどの他の抗酸化物質は、消化吸収されてから血液に乗って全身へ運ばれます。そのため、摂取してから吸収・代謝までに数時間程度かかると言われます。
水素分子は最小の分子であるため、細胞膜を通過し、細胞内のあらゆる場所(ミトコンドリア、細胞核など)に到達できます。通常、血液に乗って脳に入る物質は「血液脳関門」によって制御されていますが、水素はこの壁も突破し、脳細胞にも行き届くことが報告されています。3)
他の多くの抗酸化物質は分子が大きかったり、水溶性(水に溶ける)または脂溶性(油に溶ける)のどちらかに偏っていたりするため、水素のように細胞の隅々や脳にまで到達することは困難とされます。
水素には過剰摂取の心配がなく、安全に使用できます。その背景として、余計な分は呼気と一緒に自然に体外へ排出されること、活性酸素と反応した際の副産物は無害な「水」であることなどが考えられています。人を対象とした研究では、水素吸入を停止後10〜20分程度で体内からほとんど抜けると報告されています。2)
一方、ビタミンCなどの抗酸化物質の中には、過剰摂取による副作用や健康被害があるものが存在します。特に、脂溶性ビタミン(ビタミンEなど)は体内に蓄積しやすく、過剰摂取による副作用に注意が必要です。
上述した4つの観点(選択性、、即効性、浸透性、安全性)を、代表的な抗酸化物質(ビタミンCとビタミンE)と比較表にまとめました。
▼水素とビタミンC・Eの違い
| 項目 | 水素 | ビタミンC (水溶性) | ビタミンE (脂溶性) |
| 選択性 (除去対象) | ◎ 悪玉活性酸素のみ除去 | △ 善玉・悪玉の区別なし | △ 善玉・悪玉の区別なし |
| 即効性 (吸収速度) | ◎ 非常に速い (摂取後、わずか数分) | △ 遅い (経口摂取後2〜3時間) | △ 遅い (経口摂取後、数時間) |
| 浸透性 | ◎ 非常に高い (最小の分子で、脳や細胞核まで到達) | ○ 水に溶けやすい (血液中に拡散しやすいが、皮脂膜や細胞膜を通過しにくい) | ○ 油に溶けやすい (細胞膜には届くが、血液・脳内へは届きにくい) |
| 安全性 | ◎ 極めて安全 (過剰分は呼気で排出され、副作用報告なし) | ○ 比較的安全 (水溶性で排出されるが、高用量で胃腸障害など) | △ 注意 (脂溶性で体内に蓄積しやすいため、過剰症リスクあり) |
水素は、ビタミンCやEと異なる性質を持っている抗酸化物質であることがお分かりいただけるかと思います。
非常に優秀な抗酸化物質である水素ですが、もちろん弱点もあります。
それは、「維持しにくさ」と「可燃性」です。
水素は「圧倒的に小さい」というメリットの裏返しで、維持しにくさがあります。例えば、水素水として水中に溶けていても開封後すぐに空気中に抜けてしまいます。そのため、水素水の飲み方や保存方法には工夫が必要になります。
また、空気中では水素濃度4〜75%の状態で引火することで、爆発する危険性があるガスでもあります。そのため、高流量の水素ガスで水素吸入を行う場合などは、機器管理や室内換気など運用上の安全対策は必要です。
結論から言うと、水素と他の抗酸化物質の「併用」が最も効果的な選択肢と言えます。
なぜなら、ビタミンCやビタミンEなどは、抗酸化作用だけでなく、それ自体が体に必要な「栄養素」としての役割を持っているからです。また、こうした栄養素は健康で若々しい体を作る土台でもあります。
これらの抗酸化物質を食事からしっかりと摂取することをベースとして、プラスアルファの抗酸化物質として「水素」を取り入れるのが理想と言えるでしょう。

水素を効率的に摂取する方法として、近年注目されているのが「水素吸入」です。
水素水や水素サプリなどと比べても、短時間で大量高濃度の水素を取り込める点が大きな特徴です。また、肺から直接血液に乗って、全身への到達が早いとも言われています。水素吸入の開始後20分程度で全身に水素が行き渡ることが報告されています。3)
過去には、「先進医療B」として承認され、大学病院などで臨床研究が進められていた実績もあります。
忙しい現代人にとって、短時間で大量の水素を効率よく取り入れられる「水素吸入」は非常におすすめと言えます。
水素吸入の詳細は、「水素吸入の効果・安全性のエビデンスと始め方」をご覧ください。
今回は、水素が他の抗酸化物質と異なる点について解説しました。
水素と他の抗酸化物質の違いは、「①選択性」「②即効性」「③浸透性」「④安全性」の4点です。
ビタミンCやポリフェノールが「従来の抗酸化物質」であるならば、水素はそれらの弱点を補う「次世代の抗酸化物質」と言えます。
従来の抗酸化物質の役割も理解しつつ、新しい選択肢として水素を取り入れること。それが、これからの時代の健康と美容を支える、賢い習慣となるはずです。
※本記事は、公開時点での情報に基づいて作成しており、最新のものと異なる場合があります。予めご了承ください。
こちらの記事は参考になりましたか?
こちらの記事は参考になりましたか?